こんにちは。タムラゲン (@GenSan_Art) です。
70年前の今日 (5月23日) は、黒澤明の映画『白痴』(1951) が公開された日です。ドストエフスキーの同名小説を映像化した作品が公開70周年を迎えたの機に、数奇な運命を辿ったこの映画の不思議な魅力について、あれこれ綴っていきます。
尚、拙記事内で引用する『白痴』は、全て木村浩訳の新潮社文庫です。
.
『白痴』について
白痴
The Idiot
1951年5月23日 公開
松竹映画株式会社 (大船) 製作・配給
白黒、スタンダード、166分
スタッフ
監督:黒澤明
製作:小出孝
企画:本木荘二郎
原作:ドストエフスキー
脚本:久板栄二郎、黒澤明
撮影:生方敏夫
美術:松山崇
録音:妹尾芳三郎
録音技術:佐々木秀孝
照明:田村晃雄
音楽:早坂文雄
装置:関根正平、古宮源蔵
装飾:島田丑太郎
現像:神田亀太郎
焼付:櫻井輝代
編集:杉原よし
衣裳:田口ヨシ江
結髪:北島弘子
記録:池田義徳
演技事務:今井健太郎
出社会計:生田進啓
スチール:酒井謙一
工作:三井定義
進行:山吉鴻作
後援:札幌観光協会
美術工芸品提供:はっとり和光
キャスト
那須妙子:原節子
亀田欣司:森雅之
赤間伝吉:三船敏郎
大野綾子:久我美子
大野:志村喬
大野里子:東山千栄子
東畑:柳栄二郎
香山睦郎:千秋実
香山孝子:千石規子
香山順平:高堂国典
軽部:左卜全
香山の母:三好栄子
大野範子:文谷千代子
赤間の母:明石光代
香山薫:井上大助
その他:遠山文雄、横山準、仲摩篤美、手代木国男、小藤田正一、大杉陽一、泉啓子、秩父晴子
あらすじ
北海道へ向かう青函連絡船の中で亀田と赤間が出会います。敗戦後、戦犯として処刑されそうになった亀田は、人違いと判明して釈放された後も、癲癇性痴呆の持病を抱え、白痴同然になっていました。故郷の札幌へ帰ってきた亀田は、後見人の大野の世話になります。大野の娘・綾子は、亀田の純真さに惹かれます。ですが、亀田は、政治家の愛人として囲われていた那須妙子とも離れがたい関係になります。その妙子に激しい愛憎を抱く赤間は、亀田にも親近感と嫉妬を同時に感じています。4人の愛と憎悪が織り成す関係は、やがて悲劇を招くことになります。
映画化の経緯
『白痴』 Идиот は、ロシアの小説家フョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキー Фёдор Миха́йлович Достое́вский (1821–1881) が、1868年から1969年にかけて発表した長編小説です。
大映で『羅生門』(1950) を完成させた黒澤明が、敬愛するドストエフスキーの中でも特に思い入れのある『白痴』を敗戦後間もない北海道に翻案して松竹で映画化しました。
当初、黒澤は上映時間4時間25分の二部作を構想していましたが、松竹副社長の城戸四郎に反対され3時間2分の一本に再編集しました。この3時間版は東劇で3日間のみ上映された後、松竹の指示で『白痴』はまたもや短縮されて一般公開されました。現在、私たちが観ることが出来るのは、この2時間44分版のみです。
ドストエフスキーへの思い入れが強かったこともあり、この度重なる改編が黒澤を激怒させたのは有名な話です。今のようにソフト化などで映画を再利用するという発想の無かった時代ですので、カットされたフィルムは現在も見つかっていません。堀川弘通と熊井啓が、4時間25分の完全版フィルムが某所に現存すると証言していましたが、真相は今も不明です。
原作との比較
映像化
『白痴』は、本国ロシアやドイツ、フランスなどでも映像化されています。
現時点で私が鑑賞したことがあるのは、ジョルジュ・ランパンによる1946年のフランス映画、黒澤明による1951年の日本映画、イワン・プィリエフによる1958年のソ連映画の3本と、ウラジーミル・ボルトゥコによる2003年のテレビドラマのみです。
映画
| 公開年 | 原題 | 制作国 | 監督 | 上映時間 |
| 1921 | Irrende Seelen | ドイツ | カール・フレーリッヒ | |
| 1946 | L’idiot | フランス | ジョルジュ・ランパン | 101分 |
| 1951 | 白痴 | 日本 | 黒澤明 | 166分 |
| 1958 | Идиот | ソ連 | イワン・プィリエフ | 124分 |
| 1992 | Idiot | インド | マニ・カウル | 165分 |
| 1994 | ナスターシャ | 日本・ポーランド | アンジェイ・ワイダ | 99分 |
| 2011 | Idioot | エストニア | ライナル・サルネ | 132分 |
テレビドラマ
| 放送年 | 制作国 | 放送局 | 監督 |
| 1966 | イギリス | BBC-2 | アラン・ブリッジス |
| 1991 | インド | Doordarshan | マニ・カウル |
| 2003 | ロシア | Russia 1 | ウラジミール・ボルトゥコ |
原作と映画の登場人物一覧
原作は長編で登場人物も多いので、流石に黒澤も主要な登場人物だけに絞ったようです。プチーツィンやフェルディシチェンコのような端役だけでなく、イポリートのような重要なキャラも思い切って割愛することによって主役4人のドラマがより明確になったと思います。
| 原作の登場人物 | 映画の登場人物(俳優) |
| ムイシュキン公爵 | 亀田欽司(森雅之) |
| ナスターシャ・フィリポヴナ | 那須妙子(原節子) |
| パルフョン・ロゴージン | 赤間伝吉(三船敏郎) |
| アグラーヤ・イワーノヴナ | 大野綾子(久我美子) |
| エパンチン将軍 | 大野(志村喬) |
| リザヴェータ・プロコフィエヴナ | 大野里子(東山千栄子) |
| アレクサンドラ・イワーノヴナ | 大野範子(文谷千代子) |
| アデライーダ・イワーノヴナ | |
| トーツキイ | 東畑(柳栄二郎) |
| ガヴリーラ (ガーニャ) | 香山睦(千秋実) |
| ワルワーラ (ワーリャ) | 香山孝子(千石規子) |
| ニコライ (コーリャ) | 香山薫(井上大助) |
| イヴォルギン将軍 | 香山順平(高堂国典) |
| ニーナ・アレクサンドロヴナ | 香山の母(三好栄子) |
| マルファ・ボリーソヴナ | × |
| イポリート・テレンチェフ | × |
| プチーツィン | × |
| フェルディシチェンコ | × |
| レーベジェフ | 軽部(左卜全) |
| ヴェーラ | × |
| ダーリヤ・アレクセーエヴナ | × |
| ロゴージンの母 | 赤間の母(明石光代) |
| ケルレル | × |
| ウラジーミル・ドクトレンコ | × |
| щ(シチャー)公爵 | × |
| ラドムスキー公爵 | × |
| パヴリーシチェフ | × |
| アンチープ・ブルドフスキー | × |
| シュナイダー先生 | × |
| マリイ | × |
原作の各場面と映画の対比
ここでは、私が観たことのある3本の映画版を原作の各場面と対比してみます。
ジョルジュ・ランパンの『白痴』は上映時間が101分で黒澤の『白痴』より遥かに短く、ダイジェスト版のような印象です。ムイシュキン公爵役のジェラール・フィリップは好演していたと思いますが。
尚、イワン・プィリエフによる1958年のソ連映画が映像化したのは原作の第一編のみで、第二編以降は何故か映画化されないまま終わりました。ですが、約2時間かけて第一編を描写しているので、かなり原作に忠実な内容です。更に本場ロシアで撮られただけあって、雰囲気も良いです。ムイシュキン公爵役のユーリー・ヤコヴレフ(『不思議惑星キン・ザ・ザ』(1986) のビー)に顕著でしたが、男優陣の眼のメイクが濃く、赤い照明と相俟って『イワン雷帝・第2部』(1946) のカラー映像のように感じる場面が多かったです。
第一編
| 章 | 概要 | ランパン版 | 黒澤版 | プィリエフ版 |
| 1 | ペテルブルグ行きの列車内で、ムイシュキン公爵は、ロゴージンとレーベジェフに出会う。 | × | 〇 | 〇 |
| 2 | 公爵がエパンチン将軍宅を訪問。 | 〇 | × | × |
| 3 | 将軍とガーニャはナスターシャとの結婚について話す。 | 〇 | × | 〇 |
| 4 | トーツキイはナスターシャをガーニャと結婚させようと画策。 | × | × | × |
| 5 | 将軍夫人と3人の娘に公爵はスイスでの体験を話す。 | × | × | 〇 |
| 6 | 迫害されていたマリイの話。 | × | × | 〇 |
| 7 | 公爵がナスターシャのことを話す。ガーニャは夫人に呼び出され、アグラーヤから手紙を返される。 | × | 〇 | 〇 |
| 8 | ガーニャ宅に公爵は下宿。ガーニャと妹の口論中、公爵はナスターシャと玄関で出会う。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | ナスターシャの訪問にガーニャ達は驚く。イヴォルギン将軍がナスターシャに過去の話をする。 | × | × | 〇 |
| 10 | ロゴージン乱入。ワーリャにガーニャ激昂。止めようとした公爵が殴られる。ナスターシャとロゴージン去る。 | 〇 (ロゴージンの 出番なし!) |
〇 | 〇 |
| 11 | ガーニャは公爵に謝罪。 | × | × | 〇 |
| 12 | 公爵はイヴォルギン将軍に会うが、将軍は妾の家に行き、コーリャが公爵をナスターシャの所へ案内。 | × | × | × |
| 13 | ナスターシャの夜会。公爵来訪。フェルディシチェンコは男性客に悪事を告白するゲームを提案。 | × | × | △ (公爵の来訪のみ) |
| 14 | 悪事の告白。ナスターシャはガーニャと結婚するか否かを公爵に決めてもらう。 | △ (悪事の告白なし。後半あり) |
△ (悪事の告白なし。後半あり) |
△ (悪事の告白なし。後半あり) |
| 15 | ロゴージン乱入。公爵は自分がナスターシャと一緒になると話す。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16 | 公爵は遺産のことを明かす。ナスターシャは公爵の申し出を断る。彼女は10万ルーブルを暖炉に投げ込み、ロゴージンと共に去る。 | 〇 (暖炉の札束 なし) |
〇 (亀田の遺産を横領していた大野が改心) |
〇 |
第二編
ここからランパン版は、更に大幅な省略と脚色がされています。ナスターシャと同棲しているロゴージンの家を公爵が訪問して三角関係が強調される改編はフランス映画らしいですが(笑) また、公爵を待ち伏せていたロゴージンが公爵と交換した十字架を見てナイフを下ろします。1946年のフランスでは癲癇の描写が御法度だったのでしょうか?
| 章 | 概要 | ランパン版 | 黒澤版 |
| 1 | 夜会から半年間の出来事。 | × | 〇 |
| 2 | ペテルブルグに戻った公爵はレーベジェフ宅に寄る。 | × | × (亀田が赤間の視線に気付く場面のみ) |
| 3 | 公爵はナスターシャと別れるようロゴージンを説得。ロゴージンはナスターシャとの愛憎を語る。 | △ (ナスターシャはロゴージンと同棲中!) |
〇 |
| 4 | 十字架の交換。ロゴージンは母に公爵を紹介して別れる。 | △ (十字架の交換のみ) |
〇 |
| 5 | 公爵は町を彷徨う。ホテルで待ち伏せていたロゴージンに襲われた公爵は癲癇の発作を起こして失神する。 | △ (ロゴージンは十字架を見てナイフを下げる) |
〇 |
| 6 | レーベジェフの別荘で療養中の公爵に多数の訪問客。 | × | × |
| 7 | ラドムスキー達の訪問。 | × | × |
| 8 | 公爵を中傷する記事。 |
× | × |
| 9 | 公爵の遺産を巡る口論。 | × | × |
| 10 | イポリートの独白。 | × | × |
| 11 | 公爵を訪れる人達。 | × | × |
| 12 | リザヴェータ夫人が公爵を訪問。 | × | 〇 |
第三編
ランパン版は、ナスターシャの乱痴気騒ぎにロゴージンが乱入、ラフマニノフのコンサートに来ていたエパンチン家の前にナスターシャが姿を現し、ベンチで寝ていた公爵をアグラーヤが起こして少し話した後、そのままナスターシャとの対峙という具合に更に省略・改編されています。
| 章 | 概要 | ランパン版 | 黒澤版 |
| 1 | エパンチン家の別荘。将軍一家と公爵たちの議論。 | × | × |
| 2 | 将軍一家と公爵たちは公園で音楽を聴く。ナスターシャが現れて騒動に。 | 〇 (騒動なし) |
〇 (札幌の雪まつり) |
| 3 | 公爵はアグラーヤ、将軍、ケルレル、ロゴージンと話す。 | × | × |
| 4 | 公爵の別荘に集まった大勢の人が陽気に騒ぐ。 | × | × |
| 5 | イポリートの朗読 | × | × |
| 6 | イポリートの朗読続く。 | × | × |
| 7 | 朗読を終えたイポリートは自殺に失敗。 | × | × |
| 8 | ベンチの上で寝落ちしていた公爵はアグラーヤに起こされる。 | 〇 | 〇 |
| 9 | 別荘に戻った公爵はレーベジェフ達と話す。 | × | △ (亀田が大野夫人と話す場面のみ) |
| 10 | ナスターシャの手紙を読む公爵。ナスターシャとロゴージンは公爵に別れを告げる。 | × | △ (亀田と綾子の交流。大野家で亀田は綾子に求婚。妙子と赤間は亀田に別れを告げる。) |
第四編
クライマックスとなるアグラーヤとナスターシャの対峙です。ランパン版では、白昼、牧歌的な庭が見える別荘で、ロゴージンが呑気にトランプを積み上げている中、約2分半で終わってしまいます。その後の花嫁衣裳のナスターシャと公爵が愛を語り合う場面に約3分半もかかっていますが。ロゴージン宅でナスターシャの遺骸を見た公爵が狂ったかのように笑い泣くアップで、ランパンの映画は終わります。このラストで、ロゴージンの部屋にキリストのイコンが何枚も飾られていましたが、最も重要なホルバインの『墓の中の死せるキリスト』は出ませんでした。
| 章 | 概要 | ランパン版 | 黒澤版 |
| 1 | ガーニャとワーリャの近況。 | × | × |
| 2 | ガーニャとイポリートとイヴォルギン将軍の口論。 | × | × |
| 3 | 公爵にイヴォルギン将軍とレーベジェフが会いに来る。 | × | × |
| 4 | 公爵と話した後、イヴォルギン将軍は卒中で倒れる。 | × | × |
| 5 | 公爵はアグラーヤに求婚。 | × | △ (順序は少し前) |
| 6 | 夜会の前に公爵とアグラーヤ口論。 | × | △ (亀田が妙子の名を言おうとするのを綾子が遮る) |
| 7 | エパンチン家の夜会。公爵はキリスト教について熱弁のあまり花瓶を壊す。公爵は発作で倒れる。 | × | △ (前半の夜会で亀田が花瓶を壊す) |
| 8 | イポリートが公爵にナスターシャとの対面について話す。アグラーヤに公爵も付いていく。公爵とロゴージンが見守る中、アグラーヤとナスターシャが対峙。 | △ (アグラーヤとナスターシャの対峙のみ) |
〇 (綾子に亀田が付いていく。綾子と妙子の対峙。 去る綾子を亀田は追い、妙子は失神) |
| 9 | ナスターシャと結婚することになった公爵は、エパンチン家から絶交され、エヴゲーニィ・パーヴロヴィチからも説教される。 | × | △ (大野家で叱られる亀田のみ) |
| 10 | 公爵との結婚式当日、ナスターシャはロゴージンと逃亡。 | × | × |
| 11 | 公爵とロゴージンはナスターシャの亡骸の前で一夜を過ごす。 | △ (亡骸を見て幕引き) |
〇 |
| 12 | ロゴージンは流刑に。精神が崩壊した公爵は再び療養生活に。アグラーヤは衝動的に他の男と結婚。 | × | △ (精神が崩壊した亀田は再び療養生活に戻る。綾子は後悔の涙を流す) |
再評価されるべき『白痴』
不当な酷評
黒澤明が何度も語っていたように、不完全な状態で公開された『白痴』は「罵詈雑言」にも等しい酷評を受けたそうです。松竹の無理解によって原型を留めなくなってしまったことが、より一層この映画に対する不当な中傷や攻撃を激化させました。
一般の映画評論家だけでなく、黒澤明に関する研究書を世に出したアメリカ人評論家も黒澤版『白痴』には手厳しいです。ドナルド・リチーは、原作の「魂のほうはまるで抜けてしまった」とか「登場人物の造形に完全に失敗した」とか散々な言いようですし、スティーヴン・プリンスは、ドストエフスキーと黒澤の共通点を認めながらも “so amazingly bad” (本当に驚くほど悪い) と露骨に書き、ジェームズ・グッドウィンは、原作の逆説的な要素が映画では皮相な内容に脚色されてしまったと批判的です。
映画監督の増村保造は、映像やアクションを重視する黒澤映画は「社会を描いていない」などと決めつけて、『白痴』にも「わけの分からない表面的な描写」などと難癖を付けています。又、黒澤との対談本を出した原田眞人も、自身のブログでは『白痴』を「大失敗作」と切り捨てています。
なるほど、確かに黒澤明の『白痴』には本人も認める「いびつな」個所が少なくありません。キリスト教的価値観のロシア社会の登場人物を、同じ雪国の北海道に移し替えても戦後の荒廃した社会に生きる日本人とは少なからずズレが生じたとしても無理はありません。又、原作をかなり圧縮したとは言え、長い台詞が続く場面では、映画よりも舞台劇のように見えてくる部分もあります。そして、外国文学を翻案する手腕は、後年の『蜘蛛巣城』(1957)、『どん底』(1957)、『乱』(1985) と比べると、まだ未完成な部分があります。
ですが、型通りな価値観でこの映画を退けるには惜しいほど、黒澤の『白痴』は不思議な魅力に満ちています。公開から70年も経った今あらためて『白痴』に向き合うと、公開当時から酷評されていたのが信じられないほど惹き付けられます。
同時に、上記の様々な酷評も今となっては的外れなものが殆どだと実感します。
ドナルド・リチーは黒澤明がドストエフスキーの原作の大部分を省略したことを批判していました。ですが、原作の省略が問題なら、上記の表で対比したように、上映時間が黒澤版より短いジョルジュ・ランパンの『白痴』の方がダイジェストにしか見えない省略ぶりで、黒澤の映画は原作の重要な個所を的確に押さえていると思います。(リチーは黒澤の『姿三四郎』(1943) や『椿三十郎』(1962) を絶賛しておきながら、黒澤が富田常雄の原作を何ヶ所も省略したり、山本周五郎の『日日平安』を大幅に改作したことには触れていません。)
進行中のカットにもワイプを多用しすぎているとリチーは批判していましたが、これは松竹に強引に短縮させられてしまった傷跡なので、黒澤の腕が鈍っていた訳ではありません。映画の序盤で物語や登場人物の背景を長々と説明する字幕が出てくるのも同様です。
リチーは、黒澤版『白痴』の最も良い場面として、赤間が亀田を自分の母親の部屋に案内する場面を挙げています。その理由が「原作にはないもの」と書いていますが、これは誤りです。原作の第二編の「4」で、ロゴージンがムイシュキン公爵を自分の母親の部屋に連れていく場面がちゃんと描写されています。「黒澤はドストエフスキーに固執」いう自説に固執するあまり、リチーは初歩的な誤解までしていました。
ロシアでの高評価
日本やアメリカでは批判されることの多かった黒澤の『白痴』を高く評価したのは、他ならぬドストエフスキーの本場ロシアでした。当時のソ連の映画界でも、セルゲイ・ユトケーヴィッチ (1904-1985) や、グリゴーリ・コージンツェフ (1905-1973)、アンドレイ・タルコフスキー (1932-1986) といった名監督が黒澤版『白痴』を賞賛してました。
名作『リア王』(1971) を撮ったコージンツェフは、次のように書いています。(引用は拙訳です)
「黒澤の『白痴』は、古典からスクリーンへの奇跡的な変容だと思った。ドストエフスキーのページに生命が宿り、最も繊細な定義での言葉が具体化していた。私は、スクリーン上にロゴージンの眼を見た。正にドストエフスキーが描写した野性的で燃え盛る炭火のような眼だ。」
「私には、ナスターシャ・フィリポヴナの顔がすぐに分かった。その悲劇的な美しさも。(略)ドストエフスキーの世界の中に私がいるのが分かった。外見上は異なっていても、その精神的な動きは原作者が想像したものと同じだった。」「黒澤が何とか把握したものは、外面的な対象より遥かに重要な根源的なものである。そして、なぜ彼だけがこの難題を克服することに成功したのか?それは、原作者が執拗に書いていた”fantastic reality” (空想上の現実) をスクリーン上に表現することが出来たからだ。
映画では外見上のディテールは異なっていても、それらが原作の核心を思い出させてくれた。映画の中心は、現代のリアリティと同時に太古の宗教的な要素も含んでいた。ムイシュキン公爵の精神的世界の奇妙な平和や、ロゴージンの怒りに燃えた意識も。」― King Lear, The Space of Tragedy: The Diary of a Film Director (1977)
黒澤と親交の深かったタルコフスキーも次のように書いています。
「最良の映画化とは、私の考えでは、原作とは別の、新しい何かなのです。シェイクスピアとドストエフスキーの最良の映画は、黒澤の『蜘蛛巣城』(マクベス) と『白痴』です。
しかし黒澤はきわめて多くのものを破壊しました。まったく新しいものを創造するために、舞台を現代に移しさえしています。しかし、例えば、ドストエフスキーの小説を、逐語的に言いかえたり、図解したりしようとする映画監督よりも、黒澤はドストエフスキーの世界に近いことが分かるのです。文芸作品の映画化それ自体は、純粋の意味では、意味がないと私は思います。」(訳:鴻英良)
― 『ロシア思想』
ロシア文学者の井桁貞義も、ヨーロッパ諸国で黒澤の『白痴』が高く評価されているのを見聞きしてきたそうです。(『全集 黒澤明 第三巻』)
『白痴』の脚本を黒澤と共同執筆した久板栄二郎は、こう語っていました。
「「白痴」に対する批評はかんばしくなかったが、そんな悪口では包み切れないものを、あの作品は持っていると思う。国籍不明の人物との批評もあったが、国籍なんかをとび越えた人物、世界を描いたのだと思う。そういう意味では日本映画になかったものを投げかけていた」
― キネマ旬報増刊『黒澤明ドキュメント』1974年5月号
久板が指摘したように、コージンツェフや海外の人達は、国籍や言語の壁を越えて、黒澤映画の中にドストエフスキーの精神が見事に表現されていることを見出していたのです。
本場イギリスを始め世界中で『マクベス』の最高の映画化と絶賛されている『蜘蛛巣城』さえ増村保造は「完全に失敗している」と切り捨てていますが、結局の所、黒澤の明快な映像表現から普遍的な内容を読み取れない増村や原田こそ「表面的な」見方しかしていないと思います。ムイシュキン公爵が言うように「人間というものはおたがいに見た目ばかりで分類されてしまって、肝心なものは何ひとつ認めることができない」(第一編 3) のかもしれません。
当のドストエフスキーも『白痴』の中でこう書いています。
「作家というものはその小説や物語において、社会のある種の典型をとらえて、それを芸術的にあざやかに表現しようとつとめている。もっともそうした典型は、そっくりそのままの姿では現実にお目にかかれないが、ほとんどあらゆる場合において、当の現実そのものよりはるかに現実的なものなのである」 (第四編 1)
話が飛躍しますが、司馬遷の言葉「大楽必易」を座右の銘としていた作曲家の伊福部昭も次のように語っていました。
伊福部昭 「わかりやすくというのは、理屈がそこにない、ということじゃないんですよ。理論も哲学もあるんだけど、ちょうど果物のように、皮でくるんであって、見た目はつるっと、とても簡単な形をしていて、中にいろんな栄養やおいしい味やらが入っている、というのが望ましいわかりやすさですね」
― 『伊福部昭・音楽家の誕生』
『静かなる決闘』(1949) で黒澤明と一度だけ組んだ伊福部は黒澤と馬が合いませんでしたが、この言葉は黒澤映画の分りやすさにも当てはまるような気がします。黒澤映画の分りやすさは『七人の侍』や『用心棒』のようなアクションだけではなく、難解と思われがちな『白痴』も国籍を超えて受け入れられたのです。
それに、評論家からは酷評されたとは言え、黒澤宛に届く一般の投書は『白痴』に関するものが最も多かったそうです。最も好きな黒澤映画に『白痴』を挙げる著名人には、武満徹 (作曲家) (『カイエ』1979年4月号)、早川光 (映画監督)、中谷礼仁 (建築史、歴史工学)、笹生那実 (漫画家)、井嶋ナギ (文筆家) がいます。他にも、小倉涌 (美術家)、千葉望 (ライター)、佐藤闘介 (映画監督)、有島コレスケ (ミュージシャン) が『白痴』を高く評価しています。
評論家に賞賛される理路整然と組み立てられた作品よりも、失敗を恐れずに奮闘した黒澤の『白痴』には多くの人の心に訴えかける何かがあったのは確かです。
迫力の俳優陣
那須妙子(ナスターシャ)
黒澤明の『白痴』と言えば、原節子を真っ先に連想するほど、黒い衣裳を身にまとった彼女のスチル写真やポスターが印象的です。
ドナルド・リチーは、ナスターシャに当たる那須妙子役に原節子を起用したことを「演出上の最大の欠点」と断じていますが、果たしてそうでしょうか。もしリチーが言う当時の日本映画の「女の中の女」であった原節子を『わが青春に悔なし』(1946) や『東京物語』(1953) のような清純なイメージのみで見ていたとしたら、それは固定観念ではないでしょうか。増村保造も「原節子なんか退屈だ」などと言っていますが、彼も見る目が無いです。
更に、リチーは、妙子のメイク、髪型、ケープが、ジャン・コクトーの『オルフェ』(1950) のマリア・カザレスに酷似していると決めつけて「こっけい以外のなにものでもない」とこき下ろしていますが、これもリチーの勘違いです。多忙だった黒澤は『オルフェ』を見逃していました。事実、『オルフェ』が日本で公開されたのは『白痴』の撮影も終わりかけていた1951年4月17日でした。因みに、原作の夜会でも、悪寒を耐えていたナスターシャはケープを纏っていました。
当時の(今でも)日本の女優の中で、原節子以上に那須妙子の役にピッタリな女優は容易に想像できないほど彼女は適役だったと思います。リチーは、妙子は「傲慢さの痕跡もなく、ただヒステリックなだけ」と書いていますが、原節子の美しくも強烈な目力は、傲慢さのみならず、コージンツェフが指摘した「悲劇的な美しさ」を放って圧巻です。個人的には、小津安二郎の映画の中の御淑やかな女性より遥かに魅力的に見える原節子でした。
よく「黒澤は女性を描けない」と言われますが、黒澤映画の女性は男性顔負けの強烈な印象を残します。『白痴』だけでなく『わが青春に悔なし』でも原節子が演じた女性が現実的でないという批判を受けたそうです。ですが、現代に生きる私の眼から見れば、逆境に甘んじることなく自己を貫く女性はすこぶる現実的であり、また魅力的であります。その意味では、黒澤の女性像は半世紀以上も時代を先取りしていたことになります。
(余談ですが、映画評論家の尾形敏朗は、黒澤明は成人女性を憎悪しているという説を唱えていて、原節子が黒澤映画で演じた女性は二人とも男性キャラを破滅させる「死を招く女」だと断じています。ですが、『わが青春に悔なし』の野毛を殺害したのは軍国主義の国家権力であり、『白痴』の赤間が狂ったのも彼自身の一方的な嫉妬が原因です。八木原幸枝も那須妙子も男性たちの暴力によって苦しめられた被害者なのは明らかで、そんな彼女たちを死神のように見ることは、性暴力の被害者を蔑むかのような暴論に他なりません。)
ナスターシャ・フィリポヴナは『白痴』のもう一人の主役とも言える重要な登場人物なので、ムイシュキン公爵と同様に、他の映画の女優がどのようにナスターシャを演じたのか気になるところです。ジョルジュ・ランパンの映画のエドウィージュ・フイエールは悪女的な雰囲気は出していましたが、ナスターシャの悲劇的な側面は殆ど感じませんでした。イワン・プィリエフによるソ連映画のユリア・ボリソワは悲劇的というには健康的すぎる気もしましたが、迫力のある演技でした。ウラジーミル・ボルトゥコによるテレビドラマのリディヤ・ヴェレツェーヴァの雰囲気は影のある女性に合っていたと思います。
亀田欣司(ムイシュキン公爵)
亀田欣司役を演じた森雅之も、原節子に劣らず奇跡のような名演でした。黒澤の『羅生門』や『悪い奴ほどよく眠る』(1960) で冷酷な人物を演じた人とは俄かに信じ難いほど、無垢で善良な人物を具体化していました。
原作のムイシュキン公爵は、生まれつき癲癇持ちのため知能に障害を持ってしまいました。映画の亀田は、戦争犯罪の冤罪で死刑になりかけたショックで障害を持ってしまった設定ですが、これは原作者のドストエフスキーが処刑されかけたときの体験談を盛り込んであるのは明らかです。
ムイシュキン公爵と同じく亀田は27歳でしたので、撮影当時40歳だった森は年齢的にやや離れていましたが、映像的には意外と気になりませんでした。
リチーは、森雅之は「あわれさ」を出そうとするあまり公爵の「高貴さ」を損なっていると批判的でしたが、1947年に日本の華族制度は廃止されたので、戦後日本が舞台の映画では原作の貴族社会はそぐわないと思います。また、後述するように、原作のキリスト教的要素を全て排除したのですから、黒澤が意図した「一つの単純で清浄な魂」をこれ以上なく見事に表現した森の演技は、これで正解だと思います。
ランパンの映画でムイシュキン公爵を演じたジェラール・フィリップ (公開時23歳) は貴公子という雰囲気はありましたが、精神を患った人物という風には見えませんでした。プィリエフによるソ連映画で公爵を演じたユーリー・ヤコヴレフ (公開時37歳) は原作の描写に極力似せていましたが、眼のメイクが少し濃すぎて、神聖な人物の影に邪悪さが潜んでいるかのように見えてしまうときがありました。ボルトゥコによるテレビドラマで公爵を演じたエフゲニー・ミローノフ (放送時37歳) も原作に忠実でしたが、ヤコヴレフとは対照的に非常に自然な演技でした。
リチーが言うような公爵の「高貴さ」を果たしてどの俳優が一番うまく表現していたのか私には何とも言えませんが、フランス人やロシア人の俳優と比べても、森の演技は遜色がなかったと思います。
赤間伝吉(ロゴージン)
ロゴージンの粗野なキャラは、三船敏郎で適役だと思った人は少なくない筈です。公開当時は、この映画を「目玉映画」と揶揄した評論家もいたそうですが、コージンツェフが賞賛したように三船の目力は野性的なロゴージンそのものです。同時に、亀田に嫉妬しながらも彼の純粋さに惹かれてしまう複雑な心情も三船は見事に演じていました。
又、活舌が悪さが定評の三船ですが、『羅生門』や『七人の侍』のように怒鳴る台詞が少なかったので、『白痴』では台詞が聞き取りにくいことは殆どありませんでした。
ランパン版でロゴージンを演じたリュシアン・コエデルはミスキャストだったと思います。プィリエフ版のレオニード・パルホメンコと、ボルトゥコ版のウラジミール・マシコフはどちらも、はまり役でした。
大野綾子(アグラーヤ)
ムイシュキン公爵をからかいながらも彼の純粋さを愛するようになるアグラーヤも、『白痴』の強烈なキャラの一人です。久我美子は、潔癖であるが故に亀田とうまく接することができない綾子を好演していました。
亀田が訪問する度に綾子の感情がコロコロと移り変わる一連の場面は、この映画で私が特に好きな場面の一つです。
ランパン版のナタリー・ナティエは、ロゴージンより出番が少なく殆ど脇役あつかいでした。プィリエフ版のライサ・マクシモワは、映画が第一編のみで終わってしまったため、エパンチン家での場面しか出番がありませんでした。ボルトゥコ版のオルガ・ブディーナは、久我美子を除けば最も可憐なアグラーヤでした。
その他の登場人物
よく指摘されるように、主役4人以外の登場人物は、原作よりかなり出番が減らされたり、何人かは登場すらしません。原作では重要な役割を果たすエパンチン将軍やガーニャに相当する大野や香山は脇役となり、レーベジェフの軽部やイヴォルギン将軍の香山順平に至ってはエキストラ程度の出番でした。
黒澤の映画が当初は4時間以上の長尺だったとは言え、大長編の小説を映像化するとなると、主役4人に焦点を絞ったのは賢明な選択だったと思います。もし原作の内容をそのまま映像化するとなると、イワン・プィリエフによるソ連映画のように原作の各編を1本ずつ映画にするか、ウラジーミル・ボルトゥコによるテレビドラマのように約50分の回を10回放送するように、最低8時間以上の尺が必要になります。
それでも、上記の表で比較したように、単なるダイジェストにしか見えないジョルジュ・ランパンの『白痴』より、黒澤明の『白痴』の方が原作の内容を的確に取捨選択しています。物語のクライマックスの一つでもあるアグラーヤとナスターシャの対峙が、ランパン版では約2分半で呆気なく終わってしまったのに対して、黒澤版では約12分にも及ぶ手に汗握る場面となっているのを見ても、それは明らかです。(原作をかなり忠実に映像化したボルトゥコ版でさえ約8分です。)
それと、重要なのはドストエフスキーの原作は長い会話や心理描写にページの大半を占められているため、それを忠実に映像化すると、プィリエフの映画やボルトゥコのテレビドラマのように登場人物が喋る場面が延々と続く形になります。小説として読むのでしたら感銘を受ける語りも、映像作品として見ると果たしてそれで良いのかという疑問を覚えます。
原作の内容をどこまで忠実に映像化するかの判断や是非は人によって千差万別だと思います。ただ、もしドストエフスキーが書いた心理描写や台詞が損なわれるのが許せないというのでしたら、それはもう映像作品には期待せず原作のみを読めば事足りると言う他ありません。
黒澤明は心酔するドストエフスキーの原作に忠実であろうとしたかもしれませんが、舞台を日本に移したりするなどの脚色をした時点で、これは黒澤流に解釈したドストエフスキーの世界と受け止めるべきです。そして、ソ連の映画監督が賞賛したように、国籍の違いを超えて原作者の精神を日本人の俳優たちは見事に演じきったのは間違いないです。
早坂文雄の音楽
黒澤版『白痴』の音楽を作曲したのは、『酔いどれ天使』(1948) 以来、『静かなる決闘』を除いて『生きものの記録』(1955) まで黒澤映画の音楽を担当した早坂文雄でした。
名作の誉れ高い『羅生門』や『生きる』(1952) 『七人の侍』(1954) に挟まれた『白痴』の音楽は、あまり評価されることがありません。確かに、映像と現実音の対位法を大胆に試みた『酔いどれ天使』や『野良犬』(1949) のような目立った実験が見当たらず、映像の雰囲気に寄り添った表現が多いからかもしれません。
長大な物語に加えて、松竹のオーケストラの技術が東宝のそれより今一つだったことにも早坂は苦労したそうです。(この映画音楽の指揮は清田茂でした。)早坂が「僕としても悔ひのない仕事したつもりだったが、やりにくい仕事であった」と日記に書いたほどの労力を費やしたにも関わらず、公開された3時間版を観た早坂は、演奏と録音が悪くて落胆してしまったそうです。
それでも、早坂が作曲した『白痴』の音楽は水準以上の出来だと思います。亀田の純粋さを表現するかのような女声合唱のテーマ曲は美しく、妙子のテーマ曲も後の『七人の侍』の「志乃のテーマ曲」を思わせます。
イワン・プィリエフによる1958年のソ連映画は、ニコライ・クリューコフの音楽がかなり大袈裟だったことを考えると、早坂文雄の音楽も再評価されても良いような気がします。(2003年にロシアで制作・放送されたテレビドラマ版は、映像も音楽も非常に抑制された演出で、同じ国で撮られたとは思えないほど半世紀前のソ連映画とは対照的でした。)
『白痴』の音楽で個人的に気に入っているのは、赤間が亀田に母親を紹介した後に流れるオルゴールのような音楽です。この曲は、どことなく早坂のピアノ曲《ミュージカル・ボックス (オルゴール)》(1945) を思わせる雰囲気の旋律です。
映画音楽では『七人の侍』が有名な早坂ですが、こういう心安らぐ優しさに満ちた曲も彼の魅力だと思います。
性別と宗教を超えた黒澤明の『白痴』
性別を超えた人類愛
妙子の遺体の前で亀田と赤間が一夜を過ごす場面は、原作にかなり忠実です。
この場面の原作との些末な違いを挙げて、尾形敏朗は、那須妙子の最期も黒澤の女性憎悪の一例のように書いています。
原作では気絶したナスターシャにロゴージンがコップの水をふりかけただけだったのに対して、映画では赤間が花瓶の水を花ごと妙子にぶっかけます。又、殺害された後のナスターシャの衣類は床に散乱していただけでしたが、殺害後の妙子の衣類はズタズタに引き裂かれていました。
原作より描写がエスカレートしているので、妙子に対する憎悪が強調されていると尾形は言いますが、『野良犬』の泥まみれのズボンや『椿三十郎』(1962) の血しぶきのように、映像で分りやすくするための黒澤流の誇張した表現にも見えます。
花瓶の水を妙子にかける描写を、尾形は「サディスティックなふるまい」と書き、原節子は『わが青春に悔なし』と『白痴』の黒澤映画で「〈女〉の代表として、徹底的にいじめられ汚された」と書いていました。又、『わが青春に悔なし』等の自我を持ち自立した女性は「女が黒澤的な男に成長する〈男性化〉以外の何物でもなく」などと決め付けています。
ここで疑問に思うのは、〈男性化〉していない自立した女性を尾形がどう考えているかです。前述したように、現代の私達からみれば、八木原幸枝のように自我を持つ女性は珍しくありませんし、外国に目を向ければもっと〈男性化〉したような女性など当たり前です。いや、今では「男性的」とか「女性的」とか単純に二分化すること事態が無意味に思えてきます。小津安二郎の映画に出てくるようなお淑やかな女性しか女性と見なさず、男性なみに自己主張するのは〈男性化〉した女などと決め付けるのは、極めて時代錯誤ですし、それこそ女性蔑視ではないでしょうか。
『白痴』の原作と映画で注目すべき違いは、花瓶の水や引き裂かれた衣類といった些末な点ではありません。
黒澤明の映画では、気絶した妙子を赤間が引き受けて、亀田は綾子を追います。大野家で叱責された亀田が、赤間に誘われて、彼の部屋で妙子の遺体と対面するという流れです。
ところが、原作では、ロゴージンがかけた水で目を覚ましたナスターシャは、アグラーヤに勝利したことに狂喜してロゴージンを追い出し、何とムイシュキン公爵と結婚することが決まります。2週間後の7月のはじめに結婚式が行われますが、その場にロゴージンがいたのを見つけたナスターシャは彼と共に逃走します。方々を探した後に公爵は、ロゴージンに誘われて、彼の部屋でナスターシャの遺体と対面します。
尺の都合もあるかもしれませんが、ここで重要なのは、妙子の身を案じてながらも結婚に至らなかった亀田に対して、ムイシュキン公爵はナスターシャと婚約中にも関わらず、アグラーヤも同時に愛していると語っていることです。
しかも、ムイシュキン公爵はナスターシャのことを何度も「気〇がい」と呼んでいて、婚約中にさえ彼女の顔を「見るに耐えない」などとエヴゲーニィ・パーヴロヴィチに語っているのです。
対して、亀田は綾子に傷ついた子供の例え話をしながら比喩として「気〇がいのように」と語っただけです。黒澤明を女嫌いのように批判する評論家がいますが、少なくともムイシュキン公爵より亀田の方が妙子を誠実に案じているのではないでしょうか。
支離滅裂とも言えるムイシュキン公爵の発言に激昂したエヴゲーニィ・パーヴロヴィチは「あなたがあの女も、もうひとりの女も決して愛したことがなかったということですよ」と叱責します。この台詞が映画では省略されたこともドナルド・リチーは批判していましたが、善良な亀田が二股をかけるような真似をさせなかった黒澤の脚色は正しかったと思います。
映画が亀田と赤間の「初夜」ばかり描かれて「妙子への鎮魂など、ほとんど一顧だにされない」と、まるで黒澤が妙子を冷淡に忘却したかのように尾形は書いていますが、原作でもムイシュキン公爵とロゴージンが一夜を過ごして狂気に陥る箇所から結末までナスターシャへの鎮魂は全く一顧だにされていません。黒澤の描写を女性憎悪のように批判する前に、ドストエフスキーに文句を言うべきなのではないでしょうか。
それに、最も好きな小説家がドストエフスキーで、最も好きな小説が『白痴』という黒澤明が、その『白痴』の白眉として、この公爵とロゴージンが一夜を過ごす場面を挙げていることを考えれば、この場面を原作に忠実に描いたのは当然と言えます。
那須妙子という一人の女性を巡る三角関係のようになり、赤間は亀田を激しく憎悪しますが、同時に自分とは対照的な亀田の純粋さにも抗いがたい友情を覚えます。ムイシュキン公爵に対するロゴージンの愛憎混じった奇妙な感情は、ナスターシャに対する彼の直情的な愛憎よりはるかに複雑で興味深い描写です。
男同士の堅い友情を繰り返し描いてきた黒澤明が、ムイシュキン公爵とロゴージンの関係とその結末に惹かれたのは分かるような気がします。
黒澤明が「男性的」な映画監督であるのは議論の余地がありませんが、同時に彼の映画で活躍する女性も男性に引けを取らないほど強い自我を持っていて魅力的です。
そして、結果的に果たせなかったとは言え、男性と女性の両方に(性差や情欲を超えた)愛情を互いに抱かせた亀田は、黒澤が創造してきた登場人物の中でも際立って普遍的な人類愛を体現した人物だと思います。
宗教を超えた人類愛
『白痴』を執筆するにあたり、ドストエフスキーは「無条件に美しい人物」を創造しようとして、その唯一の実例としてキリストを挙げていいました。こうした作者の動機から、この物語の主人公であるムイシュキン公爵は、現代に蘇ったキリストとして生み出されました。原作の『白痴』には、キリスト教を巡る議論が何度も繰り返されますが、その内容について語れるほど私はキリスト教には詳しくありません。
スティーヴン・プリンスは、ドストエフスキーがムイシュキン公爵に付したキリスト教の伝統や救世主信仰を黒澤明が抜き去ったことによって、亀田は単に人当たりの良い「博愛の使徒」になってしまったと批判していました。
キリスト教が生活の中で重要な位置を占めている西洋人から見れば、黒澤版『白痴』にキリスト教的要素が皆無なことは、日本人が思う以上に重大なことのようです。
私自身もそれを感じさせる経験を二度しました。最初は、アメリカの某大学でのことでした。私がドストエフスキーを日本語訳で読んだことを話すと、ニューヨークかぶれのスノッブな白人青年に鼻で嗤われました。まるでドストエフスキーを日本語に訳すこと自体が馬鹿げていると言わんばかりの態度でした。二度目も米国で、同じく日本語訳の『白痴』を読んだことをある女性に話すと、彼女は困惑していました。日本映画など日本文化に理解や共感もある人でしたが、やはりキリスト教が浸透した文化的背景を日本語に訳せるのかどうか彼女は半信半疑な様子でした。
確かに、ロシア正教徒であったドストエフスキーの作品にはキリスト教の要素が色濃く反映されていますので、彼の作品を十分に理解するためにキリスト教の理解は不可欠なのかもしれません。
19世紀ロシアの文化的背景は現代の日本人には馴染みの薄いものかもしれませんが、私が読んだ木村浩の訳(新潮社)では、読者にも分かりやすいように細かく注釈が付けられていました。ドストエフスキーの日本語訳に懐疑的な外国人は、日本の古典文学の翻訳に疑問を持たないのか不思議です。
キリスト教的要素が『白痴』の映画に必須だと主張する人は、キリスト教徒以外は救う価値がないとでも言うのでしょうか。もし、原作のキリスト教的要素を排除することが駄目と言うなら、ドストエフスキーの反ユダヤ主義的な要素まで残すべきだとでも言うのでしょうか。
黒澤版『白痴』では、赤間の母が仏壇を拝んでいることから、原作のキリスト教が仏教に変えられていると見る西洋の評論家もいます。ですが、あくまでも一般的な日本人の生活の一部に過ぎない感じの描写ですし、亀田と赤間のお守りの交換も素朴な友情の証として描かれ、原作の十字架の交換のような宗教的な意味合いは薄められています。(とは言え、ラストで亀田と赤間が正気を失う明方に、赤間の母が鳴らす勤行の鐘の音が二人の魂を鎮魂するかのように鳴り続けたのは効果的な演出でした。)
黒澤自身は無宗教でしたので、彼が『白痴』に込めた思いが特定の宗教についてではなく、普遍的な人類愛であるのは、演出前記に記した内容から明白です。
黒澤明 「ドストエフスキイは『白痴』を計画するに当って、真に善良な人間を描きたいのだと云っている。
しかし、この世の中にそう云う人間を登場させるためにはその人物を白痴の様な病的な存在にせざるを得なかった。
全く、こんな皮肉な悲しい話はないが、この世の中では真に善良であることは馬鹿に等しい。また、そんな人間は幼児か病的な存在以外には考えられない。
しかし本当は、そう云う世の中が病気にかかっているのだ。
どうして人間は、そんな世の中をつくってしまったのだろう。
どうして人間は自分の善意を殺し、ひとの善意を踏みにじらなければ生きてゆけないのだろう。何故、この物語の主人公の様に、憎むことも疑うこともなく、単純に清浄に人を愛してゆけないのか。僕がこの作品で云いたいのはその事である。」
― 『映画パンフレット』1951年5月
黒澤が書いているように、ドストエフスキーが「白痴」という言葉を作品の題名にした意味を改めて考えてみるべきだと思います。知能に障害を持ってしまったため社会の常識からずれた言動をしてしまうムイシュキン公爵=亀田欣司は、周囲の人間から「白痴(ばか)」と呼ばれて蔑まれます。ですが、純粋な人類愛で人の心を救済しようとする主人公と、上辺だけ取り繕って猜疑心や虚栄心に満ちた社会のどちらが本当の「白痴」なのかを、ドストエフスキーと黒澤は私たちに問いかけているのです。(後年の『生きものの記録』や『乱』でも、黒澤は狂人と現代社会のどちらが狂っているのかという問いを投げかけていました。)
黒澤明の『白痴』のラストで、再び精神が崩壊してしまった亀田を見舞ってきた薫は、大野家を訪れて悲しみに沈みます。その様子を見て、兄の香山は「たかが白痴じゃないか」と嗤います。ですが、綾子は「白痴だったのは私だわ」と、自らの行いを悔い、落涙する彼女のアップで映画は締め括られます。
アグラーヤがポーランドの自称亡命伯爵と衝動的に結婚したりするなど、原作のややシニカルな終わり方と比較すると、黒澤の映画は彼が訴えたかった内容を分かりやすく終わらせた形です。これを感情的でセンチメンタルすぎる黒澤の弱点と見るのは簡単ですが、亀田を嘲笑した香山と、亀田の愛を信じた綾子のどちらが本当の「白痴」であるのか、という黒澤の問いは十分に伝わってきます。
舞台が19世紀ロシアから戦後日本へ移り、キリスト教徒の原作者から無宗教の映画監督に作者が変わったことによって、キリスト教的な救済を探求したムイシュキン公爵は、もっと素朴な人類愛を実現しようとした亀田に換骨奪胎されました。そして、特定の宗教的な要素から自由になったことによって、ドストエフスキーが描こうとしたムイシュキン公爵の善良な魂がより純粋な形で生まれ変わったのです。
(敬称略)
.
参考資料(随時更新)
『白痴 上巻・下巻』 ドストエフスキー 著、木村浩 訳、新潮社、1970年
Mellen, Joan. Voices from the Japanese Cinema. Liveright, 1975.
Kozintsev, Grigori. King Lear, The Space of Tragedy: The Diary of a Film Director. Translated by Mary Mackintosh. University of California Press, 1977.
『月刊イメージフォーラム3月増刊号 タルコフスキー、好き!』 ダゲレオ出版、1987年
『巨匠のメチエ 黒澤明とスタッフたち』 西村雄一郎、フィルムアート社、1987年
『全集 黒澤明 第三巻』 黒澤明、岩波書店、1988年
『黒澤明 集成』 キネマ旬報社、1989年
『黒澤明 集成Ⅱ』 キネマ旬報社、1991年
Prince, Stephen. The Warrior’s Camera: The Cinema of Akira Kurosawa. Princeton University Press, 1991.
『黒澤明の映画』 ドナルド・リチー、三木宮彦 訳、社会思想社、1993年
Goodwin, James. Akira Kurosawa and Intertextual Cinema. Johns Hopkins University Press, 1993.
『異説・黒澤明』 文藝春秋、1994年
『伊福部昭 音楽家の誕生』 木部与巴仁、新潮社、1997年
『キネマ旬報復刻シリーズ 黒澤明コレクション』 キネマ旬報社、1997年
『黒澤明 音と映像』 西村雄一郎、立風書房、1998年
『黒澤明 夢のあしあと』 黒澤明研究会 編、共同通信社、1999年
『評伝 黒澤明』 堀川弘通、毎日新聞社、2000年
『蝦蟇の油 自伝のようなもの』 黒澤明、岩波書店、2001年
『黒澤明 天才の苦悩と創造』 野上照代 編、キネマ旬報社、2001年
『黒澤明を語る人々』 黒澤明研究会 編、朝日ソノラマ、2004年
『KUROSAWA 映画美術 編 ~黒澤明と黒澤組、その映画的記憶、映画創造の記録~』 塩見幸登、河出書房新社、2005年
『黒澤明と早坂文雄 風のように侍は』 西村雄一郎、筑摩書房、2005年
『『トラ・トラ・トラ!』その謎のすべて 黒澤明VS.ハリウッド』 田草川弘、文藝春秋、2006年
『大系 黒澤明 第1巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2009年
『大系 黒澤明 第3巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2010年
『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』 国立映画アーカイブ 監修、国書刊行会、2020年
『公開70周年記念 映画『羅生門』展』 国書刊行会、2020年
DVD『白痴』 松竹株式会社、2002年
CD『高橋アキ/早坂文雄:室内のためのピアノ小品集』 カメラータ、CMCD-28061、2004年
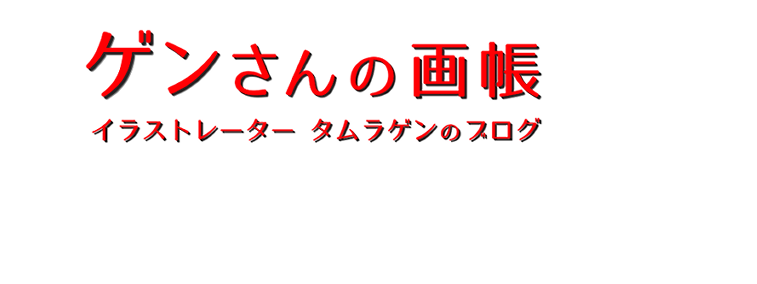






コメント