あけましておめでとうございます。タムラゲン (@GenSan_Art) です。
60年前の元日は、黒澤明の映画『椿三十郎』(1962) が公開された日です。
前作『用心棒』(1961) と同様に、『椿三十郎』も、映画館、VHS、DVD、Blu-rayで50回以上は見てきました。今見ても抜群に面白いスリルとユーモアが楽しめる快作です。
『椿三十郎』について
椿三十郎
Sanjuro
1962年1月1日 公開
東宝株式会社・黒澤プロダクション 製作
東宝 配給
白黒、シネマスコープ、96分
スタッフ
監督:黒澤明
製作:田中友幸、菊島隆三
原作:山本周五郎 「日々平安」より
脚本:菊島隆三、小國英雄、黒澤明
撮影:小泉福造、斉藤孝雄
美術:村木与四郎
録音:小沼渡
照明:猪原一郎
音楽:佐藤勝
整音:下永尚
監督助手:森谷司郎
現像:キヌタ・ラボラトリー
製作担当者:根津博
剣技指導:久世竜
キャスト
椿三十郎:三船敏郎
室戸半兵衛:仲代達矢
見張りの侍 木村:小林桂樹
(九人の若侍) 井坂:加山雄三
千鳥:団令子
黒藤 (次席家老):志村喬
竹林 (国許用人):藤原釜足
陸田夫人:入江たか子
菊井 (大目付):清水将夫
陸田 (城代家老):伊藤雄之助
(九人の若侍) 守島 兄:久保明
(九人の若侍) 河原:太刀川寛
(九人の若侍) 広瀬:土屋嘉男
(九人の若侍) 保川:田中邦衛
(九人の若侍) 関口:江原達怡
(九人の若侍) 寺田:平田昭彦
黒藤家三太夫:小川虎之助
足軽:堺佐千夫
(九人の若侍) 八田:松井健三
腰元 こいそ:樋口年子
(九人の若侍) 守島 弟:波里達彦
菊井の配下A:佐田豊
菊井の配下B:清水元
騎馬の侍A:大友伸
見張りの侍A:広瀬正一
大目付の配下A:伊藤実
大目付の配下B:宇留木耕嗣
見張りの侍B:山口博義
騎馬の侍B:大橋史典
あらすじ
江戸時代。深夜に社殿で、九人の若侍たちが次席家老と国許用人の汚職を告発しようと密談しています。若侍の筆頭・井坂は、叔父の城代家老が一向に動かないことに業を煮やし、大目付・菊井と社殿で会う約束をしていたのです。ですが、たまたま彼らの話を盗み聞いていた浪人・三十郎が本当の黒幕が菊井であると見抜きます。案の定、菊井の手の者によって包囲されますが、三十郎の機転によって難を逃れます。更に、三十郎の危惧した通り、菊井によって城代が拉致されたことが判明したので、城代の奥方と娘を救出します。血気に逸る若侍たちと三十郎は反目しあいながらも、菊井の一味と虚々実々の駆け引きを繰り返しながら城代の行方を捜します。
予告篇
個人的鑑賞記
VHS、DVD、Blu-ray
私が初めて『椿三十郎』を鑑賞したのは、学生時代にレンタルしたビデオ (VHS) でした。
数年後、アメリカのEmbassy Home Entertainment社のビデオもレンタルしてみましたが、テレビ画面のサイズにトリミングした映像でしたので落胆しました。『用心棒』や『天国と地獄』(1963) はオープニングのタイトルが英語表記でしたが、こちらは日本語表記のままでした。
こういう改竄を見てしまうと、ワイド画面の隅々を活かした構図を損ねないため、黒澤明が自分の作品のテレビ放送やソフト化でトリミングを厳禁した意図が痛いほど理解できます。
幸い、数年後には、クライテリオン・コレクションがレターボックス版のLDとVHSを発売したので安堵しました。
時が移り、21世紀を迎える頃には、VHSからDVDが映像ソフトの主流になっていきました。
2002年には、国内でも黒澤映画のDVDが続々と発売されました。中でも『椿三十郎』は『七人の侍』(1954) や『用心棒』と並ぶ売れ筋なので、他の作品よりは鮮明な映像になっていたと思います。
更に時が移り、Blu-rayが登場します。
2012年の2月に、クライテリオン・コレクションの『用心棒』『椿三十郎』のBlu-ray BOXセットを購入しました。こちらも高画質ではあるのですが、若干コントラストが強すぎるのが難点です。又、鑑賞の妨げにはなりませんが、シネスコの左右の端が少しトリミングされていました。『切腹』(1962) や『怪談』(1965) のBlu-rayでも感じましたが、暗部のディテールも見えるほど明るい映像は確かに見易いですが、作品によってはの監督や撮影監督の意図を損ねる諸刃の剣でもあります。
劇場での鑑賞
おとなの東宝チャンピオンまつり
私が『椿三十郎』を初めて劇場で鑑賞したのは、2004年に閉館する直前の高松東宝会館で開催されたオールナイト上映会「おとなの東宝チャンピオンまつり」でした。
4月3日(土)の夜から翌4月4日(日)の早朝にかけて上映されたのは、次の5作品でした。
『ハワイの若大将』(1963)
『殺人狂時代』(1967)
『ルパン三世・念力珍作戦』(1974)
『椿三十郎』
私にとって劇場で鑑賞するのが初めての作品ばかりでした。
開館前から大勢の映画ファンが詰めかけて、劇場の横の螺旋階段に長蛇の列ができていました。私も幼い頃から通っていた映画館でしたので、往年の東宝映画を立て続けにスクリーンで鑑賞するのは非常に密度の濃い体験でした。トリの『椿三十郎』のラストで「あばよ」と言い残して去る三十郎と共にオールナイト上映は終わり、朝日が昇りかけた早朝に映画館を後にしました。
2004年4月11日(日)、高松東宝会館は、1957年の開館から47年の歴史に幕を下ろし閉館しました。
午前十時の映画祭9
2018年7月11日、TOHOシネマズ岡南にて、『椿三十郎』4Kデジタルリマスター版を鑑賞しました。
『七人の侍』や『用心棒』に続いて、東京現像所の技術スタッフは、今回の『椿三十郎』4Kレストアでも見事な仕事をして下さいました。当時の初号を最も完全な形で再現することを目指した映像は実に美しかったです。冒頭の夜の場面も、クライテリオンのBlu-rayでは明るすぎましたが、今回はちゃんと夜らしく見えました。
最新のデジタル技術によって復元されたフィルムの映像と監督が意図した音楽・音響演出を体験できることだけを取っても、名作映画は劇場で見てこそ真価を発揮することがよく分かります。
4KリマスターBlu-ray (2023年4月18日追記)
2023年4月18日、ネットで購入した『用心棒』と『椿三十郎』の4KリマスターBlu-rayが届いたので、早速視聴しました。
私の自宅は4K Ultra HDを再生できる環境ではないので、4Kデジタルリマスターを2KダウンコンバートしたBlu-rayですが、我が家のテレビで見る分には十分鮮明な映像でした。東宝の旧Blu-rayは勿論、クライテリオン・コレクションのBlu-rayをも凌ぐ高画質です。
午前十時の映画祭で鑑賞した映像美を家庭でも視聴できるようになって満足です。
ただ、東宝の旧Blu-rayと同様に、解説書すら無く、DVDの特典映像「黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~」も未収録なのは残念です。せっかく映像修復のスタッフが高画質のリマスターを成し遂げても、ソフト化の仕様で相変わらずクライテリオン・コレクションに負けているところに東宝のやる気のなさが垣間見えます。
ただ、公開時に劇場で流されたソノシート音声は珍しいですし、パンフレットや宣材などのスチールギャラリーも興味深いので、特典が予告篇のみだった旧Blu-rayよりは見応えのある内容だと思います。
いずれにせよ、黒澤映画の国内盤ソフトが世界最高の高画質で発売されたのは快挙です。従来の黒澤ファンは勿論、若い世代の人達にも4Kの鮮明な映像で黒澤映画を見てもらえることを期待しています。来月以降に発売されるソフトも楽しみです。
.
『椿三十郎』の見所
『椿三十郎』と言えば、今ではラストの決闘があまりにも有名です。他にも三船敏郎の豪快な殺陣や撮影の裏話なども数多くの書籍や記事で書き尽くされた感がありますので、ここでは私が個人的に見所だと思う箇所を綴っていきます。
続編ではなく姉妹編
『椿三十郎』は『用心棒』の主人公・三十郎が再登場するので『用心棒』の続編のように語られることが多いですが、『姿三四郎』(1943) と『續・姿三四郎』(1945) のように話が繋がっている訳ではありません。
クライテリオンのオーディオコメンタリーでスティーヴン・プリンスも語っていたように、『用心棒』は三十郎が初めて登場する冒頭から彼の後ろ姿を大きく映し、彼の強さを観客に印象付けました。それに続く『椿三十郎』では、既に周知の存在となった三十郎と若侍達の対比が白眉なので、公開順に観る方が圧倒的に楽しめます。
原作との比較
山本周五郎の『日日平安』は、1954年7月の「サンデー毎日」臨時増刊涼風特別号に掲載された時代劇小説です。
黒澤明が最初に『日日平安』を脚色した時の脚本は原作に忠実な内容で、当時助監督だった堀川弘通に撮らせるつもりだったそうです。ですが、『用心棒』が大ヒットした後に黒澤が再び『日日平安』を映画化しようとした際、東宝からの要望で前作の凄腕の浪人が再び活躍する活劇『椿三十郎』へと生まれ変わったのは有名な話です。
藩の汚職を若侍たちが一掃しようとする主なプロットは同じですが、主人公の浪人・菅田平野は、剣の腕というよりは知恵を働かせるタイプで、若侍たちにも敬語で話しながらも手柄を立てて仕官のチャンスを虎視眈々と狙っているのが映画とは大きく異なります。
主人公が菅田平野から椿三十郎に入れ替わった他に、登場人物の名前も原作と映画では微妙に異なっています。
| 『日日平安』の登場人物 | 『椿三十郎』の登場人物 |
| 菅田平野 | 椿三十郎 (三船敏郎) |
| × | 室戸半兵衛 (仲代達矢) |
| 井坂十郎太 | 井坂伊織 (加山雄三) |
| 守島仲太 | 守島隼人(兄) (久保明) |
| 河原源内 | 河原晋 (太刀川寛) |
| 広瀬半六 | 広瀬俊平 (土屋嘉男) |
| 保川英之助 | 保川邦衛 (田中邦衛) |
| 関口兵次郎 | 関口信吾 (江原達怡) |
| 寺田文治 | 寺田文治 (平田昭彦) |
| 八田益太郎 | 八田覚蔵 (松井健三) |
| 寺田乙三郎 | 守島広之進(弟) (波里達彦) |
| 島田存平 | × |
| 睦田精兵衛 | 陸田弥兵衛 (伊藤雄之助) |
| 陸田夫人 おの女 | 陸田夫人 (入江たか子) |
| 千鳥 | 千鳥 (団令子) |
| こいそ | こいそ (樋口年子) |
| 菊井六郎兵衛 | 菊井六郎兵衛 (清水将夫) |
| 黒藤源太夫 | 黒藤 (志村喬) |
| 前林久之進 | 竹林 (藤原釜足) |
| 中島弥五郎 | × |
| × | 黒藤家三太夫 (小川虎之助) |
| × | 見張りの侍 木村 (小林桂樹) |
寺田文治を除く若侍の下の名前が全員異なるのは意外でした。若侍の筆頭である井坂は加山雄三が演じるので、十郎太よりは伊織の方が若者受けするからでしょうか。映画では「死ぬも生きるも我々九人」と九人であることが強調されていた若侍ですが、原作では十人でした。なぜ映画では一人減らされたのかは知りませんが、三十郎が「十一人だ!」と言うより「十人だ!」と言う方が語呂が良いからでしょうか。又、原作では兄弟なのは寺田ですが、映画では何故か守島が兄弟になっていました。
城代家老・睦田の苗字の読み方は、原作では「くがた」ですが映画では「むつた」になっていました。『赤ひげ』の「まさを」が「まさえ」になったように、読みやすさを優先したのでしょうか。下の名前も、精兵衛から弥兵衛に変えられていました。
映画では「奥方」とか「城代のかみさん」としか呼ばれなかった陸田夫人 (入江たか子) には原作では「おの女」という名前がありました。
菊井一味の一人である竹林 (藤原釜足) の名前は、原作では前林久之進でした。因みに、原作では汚職の中心人物にもう一人、中島弥五郎という留守役上席もいましたが、映画では登場しません。
逆に、菊井の懐刀である室戸半兵衛は映画の創作です。主人公が三十郎となったので、前作の卯之助と同じく仲代達矢が再び強敵を演じました。余談ですが、小林正樹の『上意討ち 拝領妻始末』(1967) でも、滝口康彦の原作『拝領妻始末』には登場しない主人公のライバル的なキャラクター浅野帯刀を仲代が演じて、主人公・笹原伊三郎役の三船敏郎と『椿三十郎』のような決闘が見せ場になっていました。
話を戻せば、こうした名前などの細かい違いがありますが、ハメットの『血の収穫』が殆ど原型を留めないほどに換骨奪胎されて『用心棒』になったように、『椿三十郎』も『日日平安』とは別の作品として楽しむのが一番だと思います。
それに、後述する『椿三十郎』の特徴を見ていけば、映画オリジナルの部分にこそ黒澤映画ならではの面白さがより明らかになると思います。
幻影と現実
『椿三十郎』の面白さが三十郎のキャラにあるのは勿論ですが、同時に公権力が必ずしも正しいとは限らないという風刺も物語を面白くしています。
『日日平安』の菅田平野は空腹のあまり狂言切腹で金銭を乞う姿で登場するように、お世辞にも格好いい侍という訳ではありません。椿三十郎も凄腕の剣豪ですが、外見が尾羽打ち枯らした浪人なので若侍達は最初は彼を不審者扱いします。
黒藤たちの汚職を知りながら放置する城代に井坂が憤っていた点は映画も原作と同じですが、その状況が大きく異なります。映画では、叔父でもある城代を見限った井坂は大目付の菊井を簡単に信じてしまい、菊井の罠に掛かりそうなところを三十郎に救われます。
社殿の中で井坂たちの話を盗み聞きしていた三十郎は「岡目八目……話してる奴より話の本筋がよくわかる」と言っていたように、貧相な城代や「立派」な見た目の大目付に会ったことがないからこそ、外見に惑わされることなく事態の真相を見抜くことが出来たのです。
猪突猛進な正義感をことごとく挫かれる若侍達や、自分が大目付に騙されていたことに気付く押入侍の可笑しさは、当たり前にように思っていた常識や公権力の政策が本当に正しいのかをさり気なく問いかけて観る者の先入観を揺さぶります。
月代と髷
時代劇の映画やドラマを見ていて、私がいつも疑問に思うことの一つが月代と髷です。
江戸時代の絵や、江戸時代末期の写真を見ても、武士や町人の丁髷は小さく控え目やな形が多いです。これに対して時代劇の髷は太く大き過ぎるように思います。真偽の程は分かりませんが、舞台上で髷を目立たせる歌舞伎の影響だという説を聞いたことがあります。
それを考えると、黒澤明の時代劇は、髷や月代にもリアリティを追求していました。
例えば、『七人の侍』では、登場人物の身分以外にも頭の形や年齢、髪の量で丁髷の形が一人一人異なっていて、各人の個性を際立たせていました。勘兵衛 (志村喬) は、映画の冒頭で頭を剃り坊主頭になります。物語が進行していくと頭に髪が少しずつ生えていくことによって月日の経過を表現していました。
『椿三十郎』で、黒澤は、室戸半兵衛のメイクに月代の広い鬘を選びました。室戸を演じた仲代達矢によると、頭頂部を広く剃った月代は老人用の鬘なので嫌がる俳優が多いそうですが、広い月代を付けることで老獪な室戸のキャラが際立っていました。
それなのに、森田芳光が監督した『椿三十郎』のリメイク版 (2007) では、また「虎屋の羊羹」みたいな丁髷に逆行していて落胆しました。
『用心棒』と『椿三十郎』の大ヒット以降、他の時代劇は斬殺音など黒澤時代劇の派手な特徴は模倣しましたが、月代と髷の地味なリアリズムは余り踏襲されていない感じがして残念です。
丁髷の形を旧来の歌舞伎型からリアリズムに徹した形に改良するだけでも、時代劇はもっと見栄えが良くなると筈です。
悪役の鏡像
和田誠は『椿三十郎』のLDやDVDの解説書では本作を好きな黒澤映画として挙げていましたが、著書『お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Part2』では『用心棒』と『椿三十郎』で仲代達矢が演じた悪役の描写が足りないとも指摘していました。他にも、室戸は劇中では誰も斬っていないのに、三十郎に翻弄されて可哀そうだという意見もありました。
これは私見ですが、『酔いどれ天使』(1948) で、志村喬が演じた主人公の医師より三船敏郎が演じたヤクザの方が目立ってしまったことの反省から悪人の描写に深入りしなくなったのではないでしょうか。『七人の侍』の野武士や『隠し砦の三悪人』(1958) の(田所兵衛を除く)山名の武将は、殆ど内面の描かれない敵として描写されていましたし。
室戸半兵衛は、登場した時点ですぐに三十郎に仕官を勧めます。大目付の役宅で三十郎に親しそうに打ち解ける室戸は、三十郎の腕を見込んだ以上の親近感を覚えているかのようにすら見えます。それだけに三十郎に騙されたことを知った室戸が激怒したのも無理からぬ話ですが、これほど三十郎に入れ込む室戸のキャラは単なる悪役や強敵とは別次元の存在のように見えてきます。
ラストで対峙する三十郎と室戸が鏡像のように左右対称になっているので、室戸が三十郎の「ネガ」的な分身であることは多くの人が指摘しています。事実、三十郎も倒れた室戸を見降ろして「こいつは俺にそっくりだ……抜身さ……こいつも俺も鞘に入ってねえ刀さ」と、まるで自分自身を斬ったかのように言っていました。
そして、この三十郎の苦渋に満ちた台詞は黒澤自身のチャンバラに対する決別でもあったのだと思います。
シリーズの是非
『用心棒』と『椿三十郎』が面白かったので、三十郎シリーズの続編を求める声は黒澤明の晩年にも絶えることはなかったようです。ですが、黒澤映画の撮影を長年担当した斎藤孝雄が、コッポラは『ゴッドファーザー』の三作目を作って失敗したので、三十郎シリーズの三作目が無くて正解だった、とある雑誌で語っていたのを覚えています。
私も斎藤キャメラマンと同意見です。
『用心棒』では楽しむかのようにヤクザたちを斬りまくっていた三十郎でしたが、城代の奥方から「抜き身の刀」のように暴力的であることを諫められたことが堪えたのか、門番も含む菊井の家臣たちを大量に惨殺したことを「とんだ殺生」と言って激怒します。室戸を斬った後、三十郎は、奥方の言葉を引用して「本当にいい刀は鞘に入ってる」と自分に言い聞かせるように若侍達を戒めます。自ら刀を封印したかのように去っていった三十郎に、その後の物語は有り得ませんでした。
惨殺音や血しぶきがその後の時代劇を決定的に変えてしまったことからチャンバラ映画の代表のように語られがちな『椿三十郎』ですが、時代劇の封建的な価値観に異議を唱えるようなコメディ仕立てに描いたことにこそ真の面白さがあります。そして、『用心棒』がチャンバラの定型をハチャメチャに破壊する面白さに満ちていたのと対照的に、『椿三十郎』は更に進んでチャンバラそのものを疑問視して否定する過程すらも第一級の娯楽作品として成立しています。
黒澤が三十郎の刀を鞘に納めてくれたおかげで、私達は『天国と地獄』と『赤ひげ』(1965) という更なる名作を見ることが出来るのです。
(敬称略)
(おまけ)特撮ゆかりの俳優
『椿三十郎』は、若侍が当時大人気だった若大将シリーズの出演者と被ることが有名ですが、同時に東宝特撮映画にも多数出演しています。
若侍
井坂役の加山雄三 (1937-) は、『エスパイ』(1974) に出演したのが唯一の特撮映画です。
守島(兄)役の久保明 (1936-) は、本多猪四郎の特撮映画の常連です。『妖星ゴラス』(1962)、『マタンゴ』(1963)、『怪獣大戦争』(1965)、『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』(1967)、『怪獣総進撃』(1968)、『ゲゾラ・ガニメ・カメーバ 決戦!南海の大怪獣』(1970) に出演しました。近年は、金子修介の『ガメラ 大怪獣空中決戦』(1995) にも出演していました。テレビは『ウルトラQ』(1966) 第23話に出演していました。
河原役の太刀川寛 (1931-) は、『妖星ゴラス』と『マタンゴ』に出演しました。テレビは『仮面ライダーV3』(1973-1974) 第36話、『スパイダーマン』(1978-1979) 第16話、『仮面ライダー』(1979-1980) 第19話、『宇宙刑事ギャバン』(1982-1983) 第34話に出演しました。
広瀬役の土屋嘉男 (1927-2017) は、黒澤映画の常連である以上に東宝特撮映画の顔として世界的に有名です。ゴジラ・シリーズでは、『ゴジラの逆襲』の田島隊員、『怪獣大戦争』のX星統制官、『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』の古川、『怪獣総進撃』の大谷博士、『ゴジラvsキングギドラ』(1991) の新堂靖明を演じました。変身人間シリーズでは、『美女と液体人間』(1958) の田口刑事、『電送人間』(1960) の岡崎捜査主任、『ガス人間㐧1号』(1960) の水野 (ガス人間)、『マタンゴ』の笠井雅文を演じました。又、『地球防衛軍』(1957) のミステリアン統領役の他に、『大怪獣バラン』(1958)、『宇宙大戦争』、『フランケンシュタイン対地底怪獣』、『ゲゾラ・ガニメ・カメーバ 決戦!南海の大怪獣』に出演しました。ウルトラ・シリーズ『ウルトラQ』第2話、『ウルトラマン』(1966-1967) 第18話、『ウルトラセブン』(1967-1968) 第14話、第15話の他に、ドラマ『日本沈没』(1974-1975) 第22話にも出演しました。
保川役の田中邦衛 (1932-2021) は、神代辰巳の『地獄』(1979) が唯一の特撮映画的な出演作でした。因みに、彼が演じた保川は若侍の中で特に三十郎に反発していたので、三十郎から「お前、丑年の生れか」と冷やかされていましたが、田中邦衛は1932年 (昭和7年) 生まれなので、申年でした(笑)
関口役の江原達怡 (1937-2021) は、『ウルトラQ』第1話に出演していました。
寺田役の平田昭彦 (1927-1984) は、特撮ファンには説明不要の伝説的名優です。『ゴジラ』(1954) で初代水爆大怪獣と心中した芹沢大助博士を演じて以来、数多くの特撮映画に出演しました。出演作は次の通りです。『空の大怪獣ラドン』(1956)、『地球防衛軍』、『美女と液体人間』、『大怪獣バラン』、『日本誕生』(1959)、『電送人間』、『モスラ』(1961)、『妖星ゴラス』、『キングコング対ゴジラ』、『海底軍艦』(1963)、『三大怪獣 地球最大の決戦』(1964)、『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』(1966)、『怪獣島の決戦 ゴジラの息子』、『緯度0大作戦』(1969)、『ゴジラ対メカゴジラ』(1974)、『ノストラダムスの大予言』(1974)、『メカゴジラの逆襲』(1975)、『惑星大戦争』(1977)、『さよならジュピター』(1984)。テレビ出演作は次の通りです。『ウルトラQ』、『ウルトラマン』、『ウルトラセブン』、『マイティジャック』(1968)、『怪奇大作戦』(1968-1969)、『愛の戦士レインボーマン』(1972-1973)、『ファイヤーマン』(1973)、『円盤戦争バンキッド』(1976-1977)、『大鉄人17』(1977)、『スターウルフ』(1978)、『西遊記』(1978-1980)、『コメットさん』(1978-1979)。
その他
椿三十郎役の三船敏郎 (1920-1997) は、東宝映画1000本記念作品『日本誕生』では倭建命と須佐之男の2役を演じました。又、『ゲンと不動明王』(1961) の不動明王や、『竹取物語』(1987) の翁も演じました。
室戸半兵衛役の仲代達矢 (1932-) は数多くの名作に出演しているので特撮映画とは無縁に思えますが、香港映画『妖獣都市 香港魔界篇』(1992) は、ある意味「特撮映画」とも言える珍品でした。因みに、椿三十郎は室戸のことを「虎」とも形容していましたが、仲代は田中邦衛と同じ1932年 (昭和7年) 生まれの申年です。
見張りの侍 木村役の小林桂樹 (1923-2010) は、『日本沈没』(1973) では田所博士を、『ゴジラ』(1984) では三田村総理大臣を演じました。
黒藤役の志村喬 (1905-1982) は、『ゴジラ』(1954) の山根恭平博士役が特に有名です。続編の『ゴジラの逆襲』(1955) でも同役を演じました。その他にも、『日本誕生』の熊曽建・兄、『モスラ』(1961) の天野貞勝、『妖星ゴラス』の園田謙介、『三大怪獣 地球最大の決戦』の塚本博士、『フランケンシュタイン対地底怪獣』(1965) の広島衛戍病院の老軍医、『ノストラダムスの大予言』の病院長を演じました。
竹林役の藤原釜足 (1905-1985) は、『超神ビビューン』(1976-1977) 第9話に出演しました。
陸田夫人役の入江たか子 (1911-1995) は、実写版『鉄腕アトム』(1959-1960) 第二部にサパタ夫人役で特別出演しました。
菊井役の清水将夫 (1908-1975) は、『黄金バット 摩天楼の怪人』(1950) と『ゴジラの逆襲』に出演しました。
黒藤家三太夫役の小川虎之助 (1897-1967) は、『ゴジラ』(1954) で南海汽船社長を演じました。
足軽役の堺佐千夫 (1925-1998) は、特撮映画では『ゴジラ』(1954) の新聞記者・萩原が特に印象的でした。その他の出演作は次の通りです。『獣人雪男』(1955)、『電送人間』、『妖星ゴラス』、『キングコング対ゴジラ』、『キングコングの逆襲』、『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』、『ゲゾラ・ガニメ・カメーバ 決戦!南海の大怪獣』。ウルトラ・シリーズでは、『ウルトラQ』第4話・第17話、『ウルトラマンA』(1972-1973) 第41話に出演しました。
こいそ役の樋口年子 (1940-?) は、『キングコング対ゴジラ』では つがるの乗客を、『モスラ対ゴジラ』では毎朝新聞社員を演じていました。
菊井の配下A役の佐田豊 (1911-?) も何気に特撮映画の出演が多く、次の作品に出演しました。
『透明人間』(1954)、『地球防衛軍』、『美女と液体人間』、『日本誕生』、『電送人間』、『モスラ対ゴジラ』、『フランケンシュタイン対地底怪獣』、『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』、『怪獣総進撃』、『ゴジラ・ミニラ・ガバラ オール怪獣大進撃』。テレビでは、『ウルトラQ』第16話、第28話、『ウルトラマン』第29話、『ウルトラセブン』第7話、『宇宙の勇者 スターウルフ』第24話に出演しました。
菊井の配下B役の清水元 (1907-1972) は、映画では『怪獣大戦争』と『地球攻撃命令 ゴジラ対ガイガン』(1972)、テレビでは『ウルトラQ』第8話と『マグマ大使』(1966-1967) に出演しました。
騎馬の侍A役の大友伸 (1919-?) が出演した特撮映画は次の通りです。『透明人間』、『ゴジラの逆襲』、『地球防衛軍』、『美女と液体人間』、『日本誕生』、『電送人間』、『キングコング対ゴジラ』、『海底軍艦』、『モスラ対ゴジラ』、『三大怪獣 地球最大の決戦』、『フランケンシュタイン対地底怪獣』。テレビでは『ウルトラQ』第6話に出演しました。
見張りの侍A役の広瀬正一 (1918-?) は、スーツアクターとしても有名で、『空の大戦争ラドン』のメガヌロン、『キングコング対ゴジラ』のキングコング、『三大怪獣 地球最大の決戦』『怪獣大戦争』のキングギドラを演じました。その他に出演した特撮映画は次の通りです。『美女と液体人間』、『電送人間』、『ガス人間㐧一号』、『大怪獣バラン』、『モスラ』(1961)、『海底軍艦』、『宇宙大怪獣ドゴラ』、『フランケンシュタイン対地底怪獣』、『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』、『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』、『キングコングの逆襲』、『メカゴジラの逆襲』、『ハウス』(1977)。テレビでは、『快獣ブースカ』第29話・第33話・第34話・第38話、『戦え! マイティジャック』第20話、『日本沈没』(1974) 第7話に出演しました。
大目付の配下A役の伊藤実 (1928-) が出演した特撮映画は次の通りです。『透明人間』、『地球防衛軍』、『美女と液体人間』、『電送人間』、『ガス人間㐧一号』、『モスラ』(1961)、『妖星ゴラス』、『キングコング対ゴジラ』、『三大怪獣 地球最大の決戦』、『怪獣大戦争』、『フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ』、『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』、『怪獣総進撃』。ウルトラ・シリーズでは、『ウルトラQ』第14話・第27話、『ウルトラマン』第30話・第32話、『ウルトラセブン』第7話・第31話、『帰ってきたウルトラマン』第4話に出演しました。
大目付の配下B役の宇留木耕嗣も特撮映画に数多く出演しました。『三大怪獣 地球最大の決戦』で初代キングギドラのスーツアクターだったと記す記事もあるようですが、諸説あります。出演した他の特撮映画は次の通りです。『ゴジラの逆襲』、『空の大怪獣ラドン』、『地球防衛軍』、『大怪獣バラン』、『日本誕生』、『宇宙大戦争』、『電送人間』、『モスラ』、『マタンゴ』、『モスラ対ゴジラ』、『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』、『キングコングの逆襲』、『ゴジラ対ヘドラ』、『メカゴジラの逆襲』。テレビでは『ウルトラQ』第8話と『日本沈没』第20話に出演しました。
騎馬の侍B役の大橋史典 (1915-1989) も特撮には縁が深く、スーツアクターや造形に留まらず怪獣テレビ映画『アゴン』の監督までしていました。因みに、『用心棒』で斬られた片腕の模型は非常に精巧で黒澤明も気味悪がったほどでした。
(敬称略)
参考資料(随時更新)
書籍
『日日平安』 山本周五郎、新潮社、1965年
『お楽しみはこれからだ 映画の名セリフ Part2』 和田誠、文藝春秋、1976年
『役者 MEMO 1955-1980』 仲代達矢、講談社、1980年
『巨匠のメチエ 黒澤明とスタッフたち』 西村雄一郎、フィルムアート社、1987年
『全集 黒澤明 第五巻』 岩波書店、1988年
『黒澤明 集成』 キネマ旬報社、1989年
『黒澤明の映画』 ドナルド・リチー、三木宮彦 訳、社会思想社、1993年
『映画編集とは何か 浦岡敬一の技法』 浦岡敬一、平凡社、1994年
『300/40 その画・音・人』 佐藤勝、キネマ旬報社、1994年
『キネマ旬報復刻シリーズ 黒澤明コレクション』 キネマ旬報社、1997年
『三船敏郎 さいごのサムライ』 毎日新聞社、1998年
『黒澤明 音と映像』 西村雄一郎、立風書房、1998年
『村木与四郎の映画美術 [聞き書き]黒澤映画のデザイン』 丹野達弥 編、フィルムアート社、1998年
『クロサワさーん! ―黒澤明との素晴らしき日々―』 土屋嘉男、新潮社、1999年
『黒澤明 夢のあしあと』 黒澤明研究会 編、共同通信社、1999年
『評伝 黒澤明』 堀川弘通、毎日新聞社、2000年
『蝦蟇の油 自伝のようなもの』 黒澤明、岩波書店、2001年
『黒澤明を語る人々』 黒澤明研究会 編、朝日ソノラマ、2004年
『KUROSAWA 映画美術 編 ~黒澤明と黒澤組、その映画的記憶、映画創造の記録~』 塩見幸登、河出書房新社、2005年
『大系 黒澤明 第2巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2009年
『未完。仲代達矢』 仲代達矢、KADOKAWA、2014年
『もう一度 天気待ち 監督・黒澤明とともに』 野上照代、草思社、2014年
『黒澤明と三船敏郎』 ステュアート・ガルブレイス4世、櫻井英里子 訳、亜紀書房、2015年
『サムライ 評伝 三船敏郎』 松田美智子、文藝春秋、2015年
『仲代達矢が語る日本映画黄金時代 完全版』 春日太一、文藝春秋、2017年
『三船敏郎の映画史』 小林淳、アルファベータブックス、2019年
『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』 国立映画アーカイブ 監修、国書刊行会、2020年
CD、DVD、Blu-ray
CD「椿三十郎」 佐藤勝、東宝ミュージック、AK-0007、2002年
DVD『椿三十郎』 東宝株式会社、2002年
Blu-ray Sanjuro. The Criterion Collection, 2010.
Blu-ray 『椿三十郎 4KリマスターBlu-ray』 東宝株式会社、2023年
ウェブサイト
「黒澤明監督作品/LDジャケット特集」 LD DVD & Blu-rayギャラリー
「椿三十郎」 LD DVD & Blu-rayギャラリー
「何度見ても面白い!黒澤明監督の傑作時代劇三作品、『七人の侍』、『用心棒』、『椿三十郎』を最も完全な形で現代に復元する」 – KODAKメールマガジン、2018年7月2日
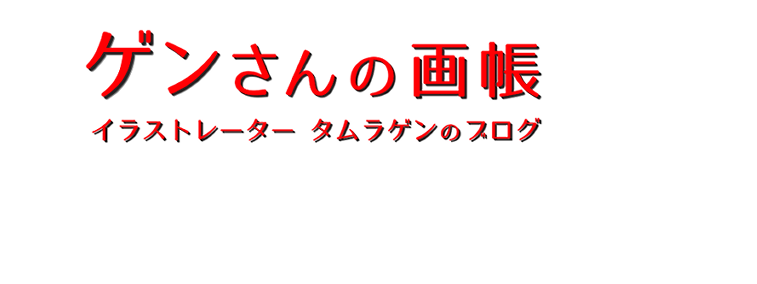


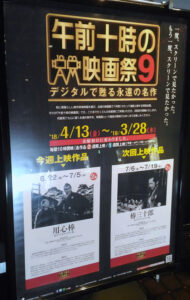





コメント