こんにちは。タムラゲン (@gensan) です。
50年前の今日 (8月2日) は、ソ連映画『デルス・ウザーラ』(1975) が日本で公開された日です。黒澤明がソ連のモスフィルムに招かれて撮った感動的な大作です。
尚、映画『デルス・ウザーラ』に関わった日本人以外のスタッフとキャストの名前の拙記事内の表記は、『黒澤明 樹海の迷宮 映画「デルス・ウザーラ」全記録1971~1975』(小学館) に準じています。
『デルス・ウザーラ』について
デルス・ウザーラ
ロシア語題名 : Дерсу Узала
英語題名 : Dersu Uzala
製作国:ソビエト社会主義共和国連邦
公開日:1975年8月2日(日本)、1976年1月5日(ソ連)
製作会社:モスフィルム「第三共同体」
協力参加:アトリエ41
配給:日本ヘラルド映画株式会社(日本)
上映時間:141分、カラー、70mm
スタッフ
監督:黒澤明
原作:ヴラジーミル・アルセーニエフ『シベリアの密林を行く』『デルスウ・ウザーラ』
脚本:黒澤明、ユーリー・ナギービン
脚本校閲:ゲオルギー・ボゴレーポフ
脚本翻訳:イリーナ・リュヴォヴァ、原卓也
製作:ニコライ・シゾフ、松江陽一
撮影:中井朝一、フョードル・ドブロヌラーヴォフ、ユーリー・ガントマン (後任)
照明:ヴラジーミル・スクリャロフ
美術:ユーリー・ラクシャ
録音:ヴェニアミン・キルシェンバウム、オリガ・ブルコーワ (後任)
編集:黒澤明
編集助手:ヴァレンチーナ・スチェパーノヴァ
音楽:イサク・シュヴァルツ
指揮:ヴァフタング・ジョルダニア
演奏:ソ連国立映画交響楽団
協力監督:河崎保
演出補佐:野上照代
助監督チーフ:ヴラジーミル・ヴァシーリエフ
助監督:箕島紀男 (演出助手)、圓井一夫 (通訳兼務)、ガリコフスカヤ・エフドキヤ (俳優担当)、アレクサンドル・ブロッキー (小道具)、スラヴァ・マクサコフ (小道具)、オリガ・エブウラノワ (記録)
記録:野上照代、オリガ・エフプラノヴァ、ヴィチェスラフ・マクサーコフ
現像:モスフィルム現像所
キャスト
ヴラジーミル・クラディエヴィッチ・アルセーニエフ:ユーリー・メフォジィエヴィッチ・ソローミン
デルス・ウザーラ:マクシーム・モングゥジューコヴィッチ・ムンズーク
(1902年の探検隊員 シベリヤ軍兵士6名)
ポリカルフ・オレンティエフ:アレクサンドル・ピャトコフ
フョードル・ハルディン (フェージャ):スタニスラフ・マリイン
セルゲイ・クルシノフ (セリョーガ):ミハイル・ブィチコフ
グリゴーリ・ウグリュモフ (グリーシャ):ヴラジーミル・イグナートフ
タラス・マルチェンコ (タラス):ヴラジーミル・セルギヤコフ
イワン・コジェフニコフ (ワーニャ):ヤニス・ヤコブソン
(1907年の探検隊員 シベリヤ軍射手4名)
ステパン・トゥルトイギン:ウラジーミル・クレメナ
パーベル・ベロノシュキン (パーシカ):ヴラジーミル・ラーストチキン
ヴァシリィ・ザハーロフ (ワーシカ):セルゲイ・シニャフスキー
アンドレイ・ボカリョフ (アンドリューハ):ヴラジーミル・フルリョフ
(同・探検隊 シベリヤコサック6名)
アレクセイ・ディヤコフ (アリョーシャ):ゲナージー・ポルーニン
ニコライ・フォーキン (コーリャ):イーゴリ・スイフラ
ミハイル・ザグルスキー (ミーシャ):ヴラジーミル・フリョスタフ
アルチョーム・エーポフ (チョーマ):ヴラジーミル・スヴェルバ
ドミトリィ・エゴロフ (ミーチャ):ミハイル・テトフ
サーシャ・ムルジン (サーニカ):ヴェニアミン・コルディン
ジャン・バオ:シュメイクル・チョクモロフ
リー・ツンビン (老中国人):ジャジャグリーシャ
アンナ・アルセーニワ (アルセーニエフ夫人):スベトラーナ・ダニエルチェンコ
ヴァロージャ・アルセーニエフ (ヴォーワ・息子):ディマ・コルシコフ
あらすじ
1902年、兵用地誌的調査のためウスリー地方を踏査していたアルセーニエフの一行は、野営中、ゴリド人(ナナイ人)の猟師デルス・ウザーラと出会います。翌朝から一行の案内人となったデルスは、長年密林の中で培った知識と洞察力で彼らに信頼されていきます。レフウ河下流で、アルセーニエフはデルスと二人だけでハンカ湖の調査に向かいますが、道に迷ってしまい、強風と豪雪に見舞われてしまいます。絶体絶命のアルセーニエフでしたが、デルスの機転で救われます。その後も苦しい行程を経て、ウスリー鉄道の線路上で、アルセーニエフの一行はデルスと別れます。
1907年、再びウスリー地方の探検に出向いたアルセーニエフの一行は、デルスと再会します。一行は、森の中で匪賊による乱獲や略奪の痕跡を見付けますが、ジャン・バオが率いる匪賊討伐隊と出会います。ある日、デルスは誤って虎に発砲してしまったことに激しく動揺します。更に、老いたデルスは視力が低下したことによって森で生きていくのが困難になってしまいます。アルセーニエフは、ハバロフスクの自宅にデルスを住まわせますが、都会での生活にデルスはどうしても馴染めませんでした。やむを得ずアルセーニエフは新型の猟銃をデルスに与えて彼を森に帰します。ですが、その銃を狙った賊によってデルスは殺害されてしまします。森に埋葬されたデルスの墓の前で、アルセーニエフは呆然と立ちすくむのでした。
製作の経緯
黒澤明の助監督を務めたことのある堀川弘通によると、1939年頃に神田の古書店で堀川がアルセーニエフの著書を目にしたのが、そもそもの発端でした。
満鉄調査部が定期的に発行していた『満鉄調査部報』に掲載されていたのを読んだ堀川は興味を持ったので購入しました。それを黒澤明にも読んでもらったところ、彼もデルスの生き様に共感して、映画化への意欲が生まれたそうです。
『白痴』(1951) 公開後、企画していた『棺桶丸の船長』が没になったので、黒澤はアルセーニエフの探検記の舞台を日本に移して映画化しようとしますが、久板栄二郎の脚本にも納得いかなかったので実現しませんでした。
『羅生門』(1950) がヴェネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞して一躍世界的な大監督となった黒澤は『生きる』(1952) や『七人の侍』(1954) などの名作を連作していきます。ですが、映画界が斜陽になるにつれ、巨額の製作費と長期間の撮影を必要とする黒澤映画は映画会社から敬遠されていきます。
日本で映画を撮れなくなった黒澤は、アメリカに活路を見出そうとします。ですが、『暴走機関車』は制作が無期延期となり、『トラ・トラ・トラ!』(1970) では監督を解任されるという挫折を味わいます。
万事休すのように見えた黒澤でしたが、ソ連で映画を撮る話が舞い込みます。この経緯について、笹井隆男が『黒澤明 樹海の迷宮』の中で検証しています。
従来はソ連側からの依頼が発端というのが定説でした。ですが、日本ヘラルド映画株式会社の当時の社長・古川勝巳と当時の宣伝部長・原正人の証言によると、1970年にベオグラード国際映画祭に出席した黒澤明と松江陽一が、その帰りにモスクワに立ち寄り、ソ連映画合作公団の総裁O・テネシビリと面談した際、映画製作を持ちかけるという段取りを、ヘラルドが根回ししていたそうです。
1973年、モスクワにて、ソ連映画合作公団、モスフィルム撮影所、黒澤明の間で『デルス・ウザーラ』の製作協定が正式に調印されました。監督の黒澤が日本人ということで、国内外では「日ソ合作」と誤解されることがありますが、製作協定は『デルス・ウザーラ』が「ソ連映画」であるという条件で合意しています。日本人のスタッフは、黒澤を含めて6人のみでした。
1974年4月4日、クランクイン。1975年4月28日、クランクアップ。同年6月13日、ダビング終了によって、映画完成。7月10日からのモスクワ国際映画祭で世界初公開されました。
『どですかでん』(1970) 以来5年ぶりの黒澤映画となった『デルス・ウザーラ』は、1975年度モスクワ国際映画祭の金賞や、米国アカデミー賞の外国語映画賞など海外で多数の賞を受賞して、黒澤の復活を世界中に印象付けました。
個人的鑑賞記
レンタルビデオ (CBS/SONY)
1989年1月28日、レンタルビデオ (VHS) で初めて鑑賞しました。
『用心棒』(1961) や『椿三十郎』(1962) 等を見て黒澤映画にハマり始めていた頃、猪俣勝人の『世界映画名作全史〈現代編〉』(現代教養文庫) で『デルス・ウザーラ』が紹介されていたのを読んで興味を持ったのがきっかけです。
初公開時にはモノクロ時代の黒澤映画との作風の違いに戸惑う声もあったそうですが、私は先に『影武者』(1980) や『乱』(1985) を見ていましたので、『デルス・ウザーラ』も晩年の作風の一つという感じで自然に受け入れられました。それに、一見淡々と進んでいくような内容でありながら、観る者を惹き付ける画面の力強さやデルスとアルセーニエフの友情に心打たれました。それ以来、『デルス・ウザーラ』は、私が最も好きな黒澤映画の一本であり続けています。
レンタルビデオ(Kino Video)、レーザーディスク(クライテリオン・コレクション)
1990年代前半、私は所用で滞米していました。
北米では、当初、Embassy Home Entertainmentからビデオが発売されていました。1994年には、Kino Videoから装いも新たにワイドスクリーン版で再発売されました。
1995年、クライテリオン・コレクションからレーザーディスク(CAV)も発売されました。勿論、ワイドスクリーンでの収録で、音声はオリジナルのロシア語と英語吹き替え版が収録されていました。
『乱』と同様に権利関係なのか、その後クライテリオンから『デルス・ウザーラ』のソフト化の話がありません。幾つかの海外メーカーから『デルス・ウザーラ』のDVDやBlu-rayは発売されましたが、クライテリオンによるソフト化を期待したいです。
DVD(アイ・ヴィー・シー)
1998年には黒澤明が他界しました。21世紀を迎えるあたりから、映像メディアもVHSからDVDへと変換していき、日本でも各社から黒澤映画のDVDが続々と発売されました。
日本では『デルス・ウザーラ』の最初のDVDは、2000年に発売されました。
輸入・発売元は、アイ・ヴィー・シー。企画・制作は、RUSSIAN CINEMA COUNCIL。日本語字幕は、ロシア映画社。企画協力は、映像文化振興協会、ロシア連邦大使館。
ディスクは、前後編に分けられた2枚組です。
気になるのは、全編が68分で後半が68分と表記されていることです。合計すると136分なので、本来の上映時間である141分より5分短いことになります。
音声は、ロシア語の他に、英語とフランス語の吹き替え版も収録されていて、全て5.1chサラウンドです。
字幕は何と13もの言語が選択できます。日本語の他に、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ヘブライ語、スウェーデン語、アラビア語、中国語、ロシア語 (英・仏音声選択時のみ) が収録されています。
画質ですが、DVD黎明期のソフトのせいか、やや荒削りな印象を受けます。普通に鑑賞する分には支障ありませんが。
その代わり、特典は、かなり豊富です。
・ウラジーミル・アルセーニエフについて(約1分)
・撮影現場(約5分)
・メイキングフォトアルバム
・ソローミンは語る
原作者について(約5分)
黒澤明監督について(約9分)
撮影について(約7分)
・フィルモグラフィー
・トレーラー「チャイコフスキー」「持参金のない娘」他
DVD(東宝)
2002年に東宝から発売されたDVD BOX「黒澤明 THE MASTERWORKS 1」に『デルス・ウザーラ』も収録され、後に単品も発売されました。
画質は、アイ・ヴィー・シー盤よりは鮮明ですし、日本語字幕も読みやすくなっています。ただ、シーン8「峡谷(秋)」で焚き火で真っ赤に照らされる木などの色彩が少し濃すぎる気がします。
特典は、東宝盤独自の内容があり、見応えあります。
劇場予告篇は、日本での特報と予告篇が収録されています。特報は、撮影中の黒澤の映像も見れます。
「黒澤明 創ると云うことは素晴らしい」は、野上照代・松江陽一・圓井一夫の対談、黒澤と中井朝一の演出中の録音や、撮影風景のカラー映像、イサク・シュヴァルツのインタビューが特に貴重です。
DVD(オデッサ・エンタテインメント)
2013年、『デルス・ウザーラ』のDVDが再び日本で発売されました。
発売元は、中央映画貿易とオデッサ・エンタテインメントです。
仕様ですが、ロシア語モノラルの音声と日本語字幕のみなのは仕方ないとしても、収録されているのは本編のみで予告篇すら収録されていません。特典など豪華な仕様だったアイ・ヴィー・シー盤と比べると寂しい限りです。それでも、新たに発売してくれるだけでもありがたいと言うべきかもしれませんが。
その代わり、画質はDVDの中では最も鮮明だと思います。モスフィルムがオリジナル・ネガからHDリマスタリングした原盤を使用しましたので、色彩も東宝盤より遥かに自然な感じがします。
その後、イタリアやオーストラリア等の国で『デルス・ウザーラ』のBlu-rayが発売されましたが、どれもリージョンコードが日本と異なるので、購入を断念していました。クライテリオンや日本でBlu-rayが発売されない現状を嘆いていると、思わぬ形で『デルス・ウザーラ』を見れることになりました。
モスフィルム公式動画(英語字幕)
何と、モスフィルムのYouTube公式チャンネル (Mosfilm) が『デルス・ウザーラ』全編を無料で公開してくれたのです。しかも、『イワン雷帝』(1944-1946) や『惑星ソラリス』(1972) 等、250本以上もの作品を公開中という大盤振る舞いです。
ディスクという物理メディアでなく配信という形式なのが時代の流れを感じさせます。本当なら大スクリーンで鑑賞すべき映画ではありますが、なかなか上映の機会に恵まれない中、高画質で『デルス・ウザーラ』を無料で視聴できるのですから、一人でも多くの人に見てもらいたいです。
原作と映画
比較表
拙記事で参考にしたアルセーニエフの原作は、1995年に河出書房新社から出版された『デルスー・ウザーラ』上下巻 (長谷川四郎 訳) です。
尚、河出文庫版は現在在庫が僅少ですので、下巻の1907年の探検を収録した『デルスウ・ウザーラ:沿海州探検行』(東洋文庫) が比較的入手しやすいかもしれません。
映画のシーンNo.は『全集 黒澤明 第六巻』(岩波書店) に準じています。
撮影されなかったり、カットされるなど欠番となったシーンは『黒澤明 樹海の迷宮 映画「デルス・ウザーラ」全記録1971~1975』(小学館) に掲載された脚本(1973年10月26日の決定稿)を参照しています。
| 原作 | 映画 (シーンNo.) | ||
| デルスー・ウザーラとの出会い 1902年の探検 | |||
| 1 | ガラス谷 | アルセーニエフ隊出発。目的は、シコトーヴォ地区の兵要地誌的調査。 | 無し |
| 2 | デルスーとの出会い | 野営中、デルス登場。当時53歳。 | 7, 8 |
| 3 | イノシシ狩り | デルス、中国人の足跡を発見した後、小屋に米と塩とマッチを残す。 | 9, 10, 11, 12, 13 |
| 4 | 朝鮮人村での出来事 | カザケーヴィチェヴォ村に着くが、朝鮮人に宿泊を断られたため野営。 | 無し |
| 5 | レフー河の下流 | デルス、湯沸かしを叱り、アルセーニエフ驚く。 | 19 叱るデルスをハルディンがからかう。 |
| 6 | ハンカ湖の大吹雪 | アルセーニエフとデルス、ハンカ湖で大吹雪に遭遇。デルスの機転で助かる。ドミトロフカ村で、アルセーニエフ隊はデルスと別れる。 | 34, 38-40, 48 |
| デルスー・ウザーラとの再会 1906年の探検 | |||
| 1 | ウスリー河をさかのぼる | 5月、アルセーニエフ隊出発。目的は、ウスリー江とイマン河の上流地帯の調査。 | 無し |
| 2 | 旧信徒の村へ | シトゥヘ河を越えて、ワンゴウ河を渡り、旧信徒の村に到着。 | 無し |
| 3 | 山越え | ウスリーの密林で道に迷う。 | 無し |
| 4 | 河から海へ | ウラジーミル湾の調査。 | 無し |
| 5 | デルスー・ウザーラ | タドシュ河上流にて、アルセーニエフ、デルスと再会。 | 53, 54 |
| 6 | アンバ(虎) | デルス、キセルを忘れる。虎の足跡に気付く。猟から帰る途中、デルスはかつて虎を撃ったことを恐れていると語る。 | 56, 72 デルス、アルセーニエフの目前で虎に発砲。 |
| 7 | リーフージン河 | デルス、天然痘で亡くなった家族のことをアルセーニエフに語る。 | 23 秋、イオズヘ河付近 |
| 8 | 呪われた場所 | アルセーニエフ、誤ってデルスを撃ってしまう。ワンゴウ河で中国人が作った罠に落ちた鹿を救う。 | 58, 59, 60 (撮影されたが、編集で削除), 61 |
| 9 | 海辺へ帰る | デルス、朝日を指さして「あれ、いちばんえらい人」と言う。 | 18 東と西の空に太陽と月 |
| 10 | アカシカの叫び | アルセーニエフ、デルス、中国人の3人でテュティヘ河沿を遡り、リャンチヘーゼ河沿いに戻る。 | 無し |
| 11 | 熊狩り | アルセーニエフ、熊を撃つ。中国人の猟小屋の納屋に、乱獲された鹿の腱が束ねられている。 | 62 (毛皮商人の小屋は撮影されたが、編集で削除) |
| 12 | 匪賊との出会い | デルス、匪賊と遭遇。ジャン・バオと出会う。 | 63, 66 |
| 13 | 森林の火事 | アルセーニエフ、木の棘を踏んで足を負傷。ダーラーザゴウがシツァ河に注ぐ場所で大きな山火事。デルス、中国人と馬を連れてきてアルセーニエフを救出。 | 無し |
| 14 | 冬の旅 | アルセーニエフ、腹痛。シホテアリニに到着。大吹雪。 | 無し |
| 15 | イマン河へ | 朝鮮人の小屋。ウデヘ人の小屋。ボートを借りる。中国人の猟師部落。 | 無し |
| 16 | 困難な状態 | イマン河を小舟で下るが転覆。食料を失う。中国人部落。ウデヘ人部落。 | 無し |
| 17 | 最後の道のり | デルス、ウデヘ人の煙に気付く。デルス、躊躇しながら弾薬を要求。アルセーニエフ、名残惜しそうにデルスと別れる。 | 46, 47, 48 |
| デルスー・ウザーラの死 1907年の探検 | |||
| 1 | 出発 | アルセーニエフ、デルスと再会。デルス、クロテン狩りで稼いだお金を実業家に騙し取られたことを話す。 | 55 |
| 2 | ジギト湾のほとり | 旧信徒の老人が、デルスがキリスト教徒でないことを語る。 | 21 (欠番) |
| 3 | 行進開始 | イオズィヘ河のほとりで、妻子の墓を見付けたデルスは、焚火の前で一人歌う。 | 24 |
| 4 | 山地にて | デルス、アンバに叫ぶ。 | 無し |
| 5 | 洪水 | 一行は、小屋の中で暴風雨が過ぎ去るのを待つ。 | 無し |
| 6 | 海辺へ帰る | デルス、過去に必要もなく虎を撃ってしまったことをアルセーニエフに話す。 | 72 ※アルセーニエフの前でデルスが虎を撃つ。 |
| 7 | シャオケムに沿って | 彗星。アルセーニエフ、デルスに「太陽とは何か」と訊く。 | 15, 16 (撮影されたが、星空と流星が技術的に困難だったため削除) 17 ※ハルディンがデルスに「太陽とは何か」と訊く。 |
| 8 | タケマ | タケマへ移動。河口近くに老中国人。対岸の部落は中国人とターズの構成。 | 無し |
| 9 | リー・ツンビン | シオテ・アリニのふもと、3つの河が合流する場所に空き地。老中国人リー・ツンビン。64歳。アルセーニエフが彼の身上話を聞く。 | 26, 27, 28, 29, 31, 32 ※主にデルスがリー・ツンビンと話す。 |
| 10 | おそろしい見つけ物 | デルスとジャン・バオーは用心深く歩く。 | 無し |
| 11 | 危険な渡河 | タケマの河口を筏で渡河。北へ。チャンリンと別れる。 | 67 |
| 12 | 朝鮮人のクロテンとり | ナイナ河の段丘のふもと、海のほとりの小屋に9人の朝鮮人。デルスの昔話。 | 無し |
| 13 | 滝 | カルトゥ山脈に登る。アルセーニエフ、ヘラジカの肉片を焚火に投げて、デルス怒る。 | 75 ※脚本でもアルセーニエフが肉片を捨てるが、本編では隊員の一人が捨てることに変更。 |
| 14 | 苦しい行進 | アルセーニエフ、病で衰弱。水雷艇グロスヌイ到着。メルズリャコフ、リウマチのため帰る。残りの隊員は7人。 | 無し |
| 15 | クスン河の下流地方 | クスン河畔にウデヘ人の小屋。クスンでジャン・バオと別れる。 | 無し |
| 16 | ソロン | タホベ河の上流にソロンの小屋。 | 無し |
| 17 | ザ・ウスリー地方の中心 | デルス、猪の臭いに気付くが、アルセーニエフには分からない。デルスには猪が見えない。 | 77 |
| 18 | デルスー運命の射撃 | ジャコウジカ発見。デルスには見えず、射撃も失敗。アルセーニエフ、デルスにハバロフスクの自宅に来るよう説得。 | 78, 80 ※虎は無関係。 |
| 19 | ヘイバートウ帰る | クスンにウデヘ人と中国人。ヘイバートウ生還。 | 無し |
| 20 | シホテ・アリニをこえて | 行き倒れた中国人の遺体を発見。 | 79 (撮影されたが、編集で削除) |
| 21 | 冬の祭日 | ダヴァシグチの河口近くにウデヘの宿営地。目隠しのゲーム。 | 23 |
| 22 | トラの襲撃 | カテタバウニに、ターズと中国人の小屋。夜、虎がテントを襲う。 | 80 ※原作のデルスは虎を撃つのに躊躇しない。 |
| 23 | 旅の終わり | ビキン河畔に、シーゴウの部落。その先に中国人化したゴリド人。カザックのゲオルギーエフスキイ村に着き、ウスリー鉄道に向かう。 | 無し |
| 24 | デルスーの死 | アルセーニエフ、ハバロフスクにある自宅にデルスを住まわせるが、都会の生活に馴染めないので森へ帰る。その後、デルスが殺害された報告を受けたアルセーニエフは、コルフォスカヤの森でその遺体を確認。埋葬に立ち会う。1910年、アルセーニエフはデルスの墓を訪ねようとするが、森林伐採のため見つけられなかった。 | 1, 2, 90, 91 ※映画は、1910年に森を再訪する場面が冒頭となり、デルスの埋葬で終わる。 |
.
主な変更点
原作を脚色した際の主な変更点は、アルセーニエフ隊が1902年、1906年、1907年の3回探検したことを、1902年と1907年の2回としたことです。探検の回数を減らすことによって、デルスとの出会いとデルスの死という分かりやすい構図になりました。
その他には、原作ではアルセーニエフ隊と同行していたジャン・バオを映画では匪賊討伐隊の隊長として別行動させています
又、原作では描かれなかったアルセーニエフの妻子が映画ではハバロフスクのアルセーニエフの自宅で登場します。これも、男二人のやり取りよりは、妻子を絡ませた方がドラマが膨らんでいました。
このように、アルセーニエフの探検記や史実を改変した個所が多数あります。
何よりも原作と映画で大きく印象が異なるのは、アルセーニエフが探検中に事細かに描写した現地の人々の生活や野生の動植物、地勢、天候など膨大な記録が大幅に割愛されていることです。
河出文庫版に掲載された小沢信男の解説によると、有楽座での試写会の後、原作の翻訳者・長谷川四郎は「歯牙にもかけない風であった」そうです。小沢も、原作の方が映画とは比較にならないほど「格段に味わいが深かった」と書いていますし。
確かに、アルセーニエフの探検記を全訳した長谷川から見れば、映画版はダイジェスト版にしか見えなかったかもしれません。
ですが、河出文庫本2冊の本編合わせて670ページに及ぶ探検記を全て映像化しようとすれば、ソ連映画『戦争と平和』(1965-1967) の上映時間6時間半なみの長尺になるかもしれません。テレビドラマなら全編を網羅できるかもしれませんが、黒澤明も手を焼いたシベリアでの過酷なロケや動植物の撮影などを実現するのは、現在の技術でも容易ではないと思います。
実は、黒澤明も見せ場となりそうな場面を撮影はしていたのですが、撮影所の現像ミスや上映時間の制限という数々の要因が重なって現在の形となりました。
とは言え、当初の構想とは異なる形になったとしても、黒澤の『デルス・ウザーラ』は、あらゆる要素を極力削りシンプルな構成となったことによって、素朴で感動的な物語になったと思います。
このように原作を脚色したことについて、黒澤は「なぜならば、先ず、映画は映画でなければならないからである」と『デルス・ウザーラ』前記に書いています。(『キネマ旬報』増刊5・7号 1974年5月)
(今年話題になった李相日の映画『国宝』も、文庫本上下巻約800ページに及ぶ吉田修一の原作から多くの要素を削って、喜久雄 (吉沢亮) と俊介 (横浜流星) の二人に焦点を合わせた構成に纏めていたのを思い出しました)
余談ですが、ハリウッド映画を妄信する嫌味な大人が私の身近にいました。『影武者』などの黒澤時代劇が「史実と違う」などと姑のようにネチネチと難癖をつけていたくせに、『風と共に去りぬ』(1939) や『クール・ランニング』(1993) などの洋画が史実と異なることには全く考えが及んでいませんでした。そんな彼が珍しく褒めた『デルス・ウザーラ』も史実と異なることを知ったとしても、ヒステリックな妄言を吐くことは容易に想像できます。
デルスとアルセーニエフの友情
映画評論家の尾形敏朗は、最も好きな黒澤映画に『デルス・ウザーラ』を挙げていて、公開時に見たときは号泣するほど感動したそうです。
著書『巨人と少年 黒澤明の女性たち』で、尾形は、赤ひげとデルスを対比させています。三船敏郎が演じた赤ひげが完全無欠の〈巨人〉であったのと対照的に、ムンズクが演じたデルスは謙虚で「自然で等身大の人間味にあふれている」ので、赤ひげの演説よりデルスの片言の語りの方が受け入れられやすい、と尾形は書いています。
映画から受ける印象だけでしたら、確かにそうでしょう。ですが、原作から受ける印象は少し異なります。
原作でもデルスとアルセーニエフの二人は硬い友情で結ばれていましたが、映画は原作以上に美化して描かれています。原作では、アルセーニエフはデルスに軽口を叩いたり、デルスはアルセーニエフに対して立腹したり厳しく叱ったりすることがありました。
映画では、アルセーニエフはより常に柔和な物腰の紳士で、デルスもアルセーニエフに対してだけは決して声を荒げることはありません。
特に顕著なのが、台詞を喋る人物の変更です。上記の原作と映画の比較表を見ても明らかなように、原作のデルスを呆れさせたり立腹させたりしたアルセーニエフの言動は、映画では全て隊員たちの軽薄な言動に変更されています。
この変更は、ハバロフスクのアルセーニエフの自宅でも同様です。街での規則をデルスに教えて怒らせるのは、アルセーニエフ本人ではなく、妻という描写にされています。
ところで、アメリカの映画評論家ジョーン・メレン (Joan Mellen) は、ドナルド・リチーの著書『黒澤明の映画』で、『どですかでん』と『デルス・ウザーラ』の項を執筆してきますが、両作品に対してかなり否定的です。彼女は、『デルス・ウザーラ』では男性ばかり描写されて女性が殆んど出てこないことにも不満を漏らしていました。
ですが、そんなことを言われましても、男性のみで編成されたアルセーニエフ隊の探検記が原作なのですから、男性ばかりの映画になっても不自然ではありません。メレンはアルセーニエフの妻アンナが夫の手も繋がないので人形のようだとも批判していましたが、別にアルセーニエフの夫婦愛がテーマではありません。それに、原作では登場すらしないアンナの出番を創作したのですから、メレンの批判は全く的外れです。
又、メレンは、アルセーニエフとデルスが仲良くしていることを、まるで「男同士のラブストーリー」だと揶揄するように書いていたのには呆れました。困難な探検を切り抜けてきた男たちの美しい友情というものが彼女には理解できなかったようです。
活劇から「枯淡の映画」へ
『樹海の迷宮』で、笹井隆男が『デルス・ウザーラ』の脚本が完成するまでの過程を検証しています。
脚本執筆の大まかな流れは次の通りです。
1973年4月10日、黒澤明と井出雅人の二人で執筆開始。同年4月28日、第一稿 (全124シーン) 脱稿。ロシア語に翻訳され、ソ連の脚本家ユーリー・ナギービンによって改訂。
8月30日から9月11日にかけて、黒澤は野上照代、河崎保、箕島紀男と共に、ナギービンによる改訂版を書き直す脚本合宿。これ以降、井出雅人は不参加の模様。
9月14日、黒澤による「第二稿」(全110シーン) 脱稿。
10月17日、ナギービン来日。10月22日、黒澤とナギービンによる激論。
10月26日、黒澤による「決定稿」(全101シーン) 脱稿。
従来は、第一稿をナギービンが活劇風に書き直したので黒澤が立腹したという過程として知られていました。ですが、各段階の脚本を検証した笹井によると、意外にも最も活劇的な要素が多いのは第一稿であり、ナギービンによる修正を経た第二稿では活劇的な要素が削られていたそうです。
完成した映画を見た井出雅人が「黒澤流の壮大な活劇を期待していたのに、裏切られた感じだった」と堀川弘通に語ったのも、第一稿の執筆以降の改訂作業に参加していなかったからかもしれません。
興味深いのは、第一稿から削除された場面の内、二つは1961年の映画版『デルス・ウザーラ』では映像化されていたことです。
一つは、アルセーニエフが木の棘を踏んで足を負傷。更に山火事が迫ってきますが、アルセーニエフは動けないので、デルスは中国人と共に馬を連れてきて彼を救出する場面。原作は、1906年の探検の「13 森林の火事」に該当します。
もう一つは、イマン河を小舟で下る途中で転覆してしまい、食料を失ったアルセーニエフの一行が飢餓に苦しむ場面。原作は、1906年の探検の「16 困難な状態」に該当します。
これは私の推測でしかありませんが、上記の場面は、既に1961年版で描かれていたので、重複を避けるための改訂だったのではないでしょうか。
ともあれ、完成後に日本ヘラルド映画の社長・古川勝巳が「枯淡の映画」と評した黒澤の『デルス・ウザーラ』は、第一稿執筆という最初期の段階では「枯淡」どころか、活劇的な要素も盛り込んだ従来の黒澤映画に近い内容が構想されていたのです。それが、脚本の改訂を経て、実際の撮影でもシベリア・ロケの過酷な自然や機材の不備など様々な要因が積み重なって、現在私たちが見る『デルス・ウザーラ』へと成熟していきました。
『デルス・ウザーラ』雑感
「枯淡の映画」の裏側には喧騒の現場
かつて映画評論家の猪俣勝人は、黒澤映画を評価しつつも、その「過剰表現」に拒否反応を示していました。ですが、『デルス・ウザーラ』の静謐な作風に感動した猪俣は、黒澤が「真の映画作家」に成長したと賛辞をおくっていました。
猪俣は1979年に他界したので、翌年公開の『影武者』を見たら、どう反応したのか気になります。恐らく、従兄弟で同じ映画評論家の田山力哉と同様に否定的な反応を示したような気がします。
同様に、1994年の『異説・黒澤明』(文藝春秋) の座談会で、尾形敏朗と映画監督の早川光は『デルス・ウザーラ』を賞賛しつつも、『影武者』以降の黒澤が以前の作風に戻ったことに合点がいかない様子でした。(もっとも、先述した通り、脚本第一稿の段階では活劇的な要素もありましたが)
黒澤の助監督を長年務めた堀川弘通も、黒澤が『影武者』で「元の黒澤流」に戻ったのを不思議に思い、黒澤の長女・和子に質問したところ、ソ連での撮影中は両方の腎臓が弱っていたために「ネバレなかった」が、入院して腎臓が完治した後は元気が戻ったから、と答えられたそうです。それだけが原因ではないかもしれませんが、案外、第三者が「東洋思想」などと勝手に想像することより信憑性がありそうです。
確かに、1971年12月22日に自殺未遂をおこし、年齢も60代半ばになりかけていた当時の黒澤の健康状態は芳しくなかったようです。『デルス・ウザーラ』撮影中の黒澤の写真を見ても、普段より痩せていたのが分かります。
又、モスフィルムが黒澤の芸術上、創造上の意見を全面的に尊重してくれて、映画会社の首脳部との軋轢が殆ど無かったので、撮影終盤の頃の黒澤は「今までで一番楽だ、といえるかもしれない。(笑)」と上機嫌に語っていました。(『キネマ旬報』1975年5月下旬号)
ですが、野上照代の2001年の著書『天気待ち 監督・黒澤明とともに』(文藝春秋) によると、実際の撮影は「一番楽」どころか「一番過酷」とも言えそうなほど苦労の連続だったそうです。
『デルス・ウザーラ』東宝盤DVDの特典映像でも、野上はソ連での撮影を『七人の侍』と並んで最も大変だったと語っていました。黒澤自身もこのときの苦労を忘れないように、『デルス・ウザーラ』撮影中にかぶっていた帽子を、その後も最後の仕事までかぶり続けました。
更に、2015年に出版された『黒澤明 樹海の迷宮 映画「デルス・ウザーラ」全記録1971~1975』(小学館) に掲載された『デルス・ウザーラ』撮影日誌に目を通せば、黒澤の「天皇」ぶりはいつもと変わらないどころか、それ以上に荒れていたことが伺えます。
『乱』の撮影中のある朝、二日酔いを理由に黒澤がその日の撮影を中止して主演の仲代達矢を立腹させたという逸話はまだ苦笑できるレベルでしたが、『デルス・ウザーラ』の撮影中はそれとは比較にならないほど泥酔して撮影を中断することがしょっちゅうでした。
その上、極寒のシベリアでのロケという重労働で撮ったフィルムが現像所のミスで台無しになることが繰り返され、黒澤を普段以上に激怒させます。そして、少数の日本人スタッフが黒澤の八つ当たりの被害にあいました。特に、キャメラマンの中井朝一が四六時中怒声を浴びせられる様は、日誌を読んでいるだけで気分が悪くなりそうで、中井に心底同情しました。
黒澤の身辺の世話をしてくれた野上照代の献身ぶりにも頭が下がります。その野上も、黒澤の癇癪の被害にあいます。1975年1月14日、アルセーニエフ市ハラザ山でのロケがうまくいかなかった後、不機嫌な黒澤はホテルの部屋で泥酔しました。せっかく野上がお粥を作って持って行ったのに、黒澤はその器を野上にお粥の器を投げつけてしまいます。当然、激怒した野上でしたが、翌朝、黒澤が謝罪したことで和解したそうです。
黒澤を心から尊敬していたユーリー・ソローミンでさえ、1974年10月16日、野生の虎を酷使する撮影には耐えかねて、動物保護協会の会員として降板も辞さないと抗議したほどです。
過度の飲酒による撮影中断、度重なる朝令暮改や責任転嫁、そして止むことのない怒声。『樹海の迷宮』に特別寄稿した池澤夏樹も「黒澤の酩酊や八つ当たりはまるで人格崩壊のように見える」と呆れていました。
全盛期の黒澤明の演出の厳しさは、東宝で活躍していた頃から既に有名でした。黒澤組の忠実なスタッフの支えもあって上手く作用していた黒澤のワンマンな演出は、『トラ・トラ・トラ!』の日本パートを撮っていた東映京都撮影所では、外部スタッフから「奇行」として見られて、遂には監督を解任させられてしまいます。再起を賭けた『どですかでん』について、黒澤は撮影中に怒ったことがないことをアピールしていましたが、助監督の撮影日誌抄によると、撮影初日から雷が落とすなど、いつもと変わらない巨匠のようでした(汗) 『デルス・ウザーラ』の後で10年ぶりに日本で撮った『影武者』でも、撮影中に俳優たちに怒鳴り散らす様子がNHK特集「黒澤明の世界」(1979) にも映っていました。
こうして俯瞰して見ると、いくらシベリアの大自然の中で撮った『デルス・ウザーラ』が静謐な感動作になったからと言って、この映画の撮影中のみ黒澤の演出まで別人のように変わると想像する方が不自然です。
私は黒澤明に直接会ったこともありませんし、撮影現場での黒澤の様子も予告篇やメイキングなどの映像でしか見たことがありません。多くの関係者によるルポやインタビューなどを読んで判断するしかないのですが、撮影現場での黒澤の厳しい演出や激しい癇癪は、『トラ・トラ・トラ!』以前から日常茶飯事で、東映京都撮影所での「奇行」も黒澤にとっては特別なものではなかったようです。
勿論、一般的な常識から見れば、スタッフやキャストを激しく面罵する黒澤の演出はパワハラそのもので、癲癇から来る癇癪ということを考慮しても異常でしかないでしょう。仮に私がスタッフだったとしても、一日ももたずに根を上げてしまうと思います。
今でも『デルス・ウザーラ』は感動的な映画だと思いますが、撮影中の黒澤明の横暴を知れば知るほど黒澤本人に対する心証が損なわれてしまったのも事実です。
ですが、そうした黒澤の行いの是非はここでは問いません。
もし黒澤明の厳しい演出姿勢を理由に黒澤映画そのものを否定するのでしたら、溝口健二、ジョン・フォード、スタンリー・キューブリック、ウィリアム・フリードキン、高畑勲、宮崎駿、相米慎二、ジェームズ・キャメロンのように黒澤に勝るとも劣らない厳しい監督が撮った映画も否定しなければ倫理的な整合性が取れません。(ハリウッド映画やクラシック音楽を妄信する例の嫌味な大人がそうしたダブルスタンダードな偽善者でした) 映画以外のジャンルでも、カラヴァッジョやドビュッシーやピカソのように、人間としては最低でも歴史に残る作品を残した芸術家は少なくありません。
作品の価値と作者の人格をどれだけ分けて判断するかは難しい問題です。
それでも、たとえ理想や綺麗事だと言われようとも、あらゆる職場において、パワハラ、セクハラ、モラハラなどの悪事は根絶されるべきです。
近年の某ミニシアターのパワハラ問題や某映画監督による性加害事件のように、映画を免罪符にして罪なき人達が搾取・虐待されることは断じて許してはなりません。
デルスのエコロジー
高度経済成長期の負の遺産である水俣病や四日市ぜんそく等の公害は、黒澤明が『デルス・ウザーラ』を撮っていた1970年代前半当時もまだ深刻な社会問題でした。水木しげるは漫画『コケカキイキイ』(1970-1971) で公害問題を描き、当時子供向けになっていたゴジラ映画でさえ『ゴジラ対ヘドラ』(1971) に公害怪獣を登場させていました。
黒澤も『デルス・ウザーラ』について、環境破壊の問題や「自然と調和した文化」の重要性などを盛んに語っていました。
脚本改訂の段階では、ラストシーンに「自然に帰ろう」と訴えるために、世界の公害の映像を撮ったり、多国籍の映画監督の名前をクレジットするという案もあったそうです。ですが、完成した映画は、デルスの墓に建てられた杖のアップというシンプルな映像で幕を閉じます。
私も、この素朴な終わり方で大正解だと思います。殊更に自然保護などの「メッセージ」を掲げなくても、生前のデルスが自然と共に生きてきたことをアルセーニエフと共に思い出すだけで、この映画で黒澤が訴えたかったことは十分に感じられる筈です。
『デルス・ウザーラ』のエコロジーを考える上で、特に印象的な場面がシーン20「湖畔の小休止」です。当初の予定では、隊員たちが鴨を撃とうとする場面でしたが、撮影が困難なため、酒瓶を撃つ場面に変更されました。
注目すべきは、デルスが射撃に反対する理由です。鴨は肉が硬くて食べれないので鴨の真下の水中を狙い、酒瓶も森の中には無いものですので壊すのは勿体ないというので瓶を吊った紐を狙い、どちらも見事に命中させます。
デルスも猟師ですが、生活に必要最低限の狩りだけをして無益な殺生はしませんし、生き物でなくても無駄に物を壊したりはしません。乱獲や略奪を繰り返す匪賊に憤慨するのも当然です。
又、デルスは隊員たちが食べ残しの肉を焚き火に捨てることにも立腹していました。人間以外にも森の動植物の食べ物となるから、食べ残しも無駄にはしないのです。因みに、黒澤明の娘・和子によると、明治生まれの黒澤は、食材を食べ尽くした後は、生ゴミを分別して土に戻るものは全て埋めて処理していたそうです。(『黒澤明の食卓』小学館)
こうしたことも踏まえて見ると、『デルス・ウザーラ』は環境問題は勿論、フードロス対策についても示唆に富んだ作品と言えます。
ところで、黒澤の『デルス・ウザーラ』に対する批判は、作品全体の否定と後半のみ否定的という二通りある印象を受けます。
前者は、映画評論家の石川三登志や田中英司のように的外れな難癖をつけている人達です。1991年に黒澤と対談した映画監督の原田眞人も、ウィリアム・フリードキンの『恐怖の報酬』(1977) のことを「『デルス・ウザーラ』と比較されそうな超リアルな退屈大作」と書いて、『デルス』のことも間接的に酷評していました。(『週刊朝日』1978年3月24日号)
そして、映画前半を称賛しつつも後半に批判的な評論家としては、『キネマ旬報』(1975年8月下旬号) の品田雄吉や、『ニューヨーク・タイムス』(1976年10月5日) のリチャード・エダー (Richard Eder) がいます。
『デルス・ウザーラ』そのものを酷評したジョーン・メレンに至っては、後半、特にアルセーニエフの自宅での場面がまるで「アマチュアくさい」ので、ここだけソ連の助監督に撮らせたのではないかと疑うなど、酷い書きようでした。
品田はまだしも、アメリカ人のエダーやメレンの批判の行間からは、西洋の文明が未開の猟師を「傷つける」ものとして否定的に描かれることが我慢ならないような苛立ちを感じます。
後述するように、これこそ西洋の文明がそれ以外の文化や自然より高度なものだと思い込む驕りではないでしょうか。
もし、アルセーニエフの自宅でデルスが苦しむのが、前半ほど楽しく見れないと感じたのでしたら、それこそ黒澤が狙った通りの効果ではないでしょうか。確かに、黒澤はアルセーニエフの自宅のセットには不満足でしたが、却ってそれが「箱の中」にデルスが閉じ込められて生彩を失っていくことを的確に表現していると思います。
エダーが書いたように、前半だけで終わっていれば、それはそれで感動的かもしれませんが、黒澤が描こうとしたのはそんな陳腐な物語ではありません。
人間も自然の一部であることを忘れて環境破壊を繰り返すことへの危機感を覚えていた黒澤が訴えたかったことが後半にこそ込められていたのは明白です。密猟や乱獲による生態系の破壊や、デルスを埋葬した場所が都市開発による森林伐採によって分からなくなっていたというのも、極めて現代的な環境問題です。
過去から現代に繋がる物語である以上、『デルス・ウザーラ』は自然と共に生きた猟師に対するノスタルジーだけでは終わらず、破壊されていく自然と共に、彼が傷つき、非業の最期を迎えることによって、私たちの心に自然とどう向き合っていくかという問いを残すのです。
デルスのアニミズム
映画『デルス・ウザーラ』の中でも特に印象的な映像なのが、70mmワイド画面の中央でアルセーニエフとデルスが見上げる空の両端に太陽と月が輝く場面です。
太陽と月を指差しながらデルスはアルセーニエフに言います。「あれ(太陽)いちばんえらい人。あの人死ぬ、みんな死ぬ。あれ(月)二番目にえらい人」
原作の該当箇所は、第9章「海辺へ帰る」です。1906年の二度目の探検中、デュティへ河河口の海辺で野営した翌朝、アルセーニエフが水平線から昇る朝日の美しさに感嘆した後、デルスが太陽を指さして言います。
デルスが「あれ、いちばんえらい人」と言うのは同じですが、それに続く彼の言葉は原作では「陸も人。陸の頭―むこう(彼は北東をさした)。足―むこう(彼は南東をさした)。火と水も、二人の強い人。火と水、死ぬと、その時、みんないっぺんに終り」となっていました。
このアニミズムに満ちた言葉に「多くの思想もまたふくまれていた」と、アルセーニエフも共感していました。
原作の多くを割愛した映画『デルス・ウザーラ』で、黒澤が最後まで強調していた要素が、このデルスのアニミズムでした。
デルスが初めてアルセーニエフ隊の前に姿を見せたとき、焚火の炎に対して人間のように語りかけます。その後も、
『デルス・ウザーラ』の脚本には完成版に残らなかった場面が幾つかありますが、個人的に興味を持ったのは、シーン16「野営地」と、シーン21「旧教徒の家 (秋)」です。
シーン16「野営地」は、巨大な流星を見た隊員たちが、大洪水や戦争の前兆だと色めき立っている中、デルスは「星、ひとつ、落ちた」と興味なさそうに言っただけでした。アルセーニエフは、デルスが自然現象を「単純にあるがままに判断した」ことに感心していました。
この場面は撮影されましたが、星空と流星の合成が困難であっために、最終的にカットされました。他の活劇的な場面を脚本の段階から外したのに対して、この場面を最後まで残そうとしたところに黒澤ならではのこだわりがあった筈です。
それは「幻想と現実」です。前作『どですかでん』のように顕著ではなくとも、他の黒澤映画に頻出するこのテーマがこの短い場面に凝縮されています。『蜘蛛巣城』のように、目先の現象に根拠のない意味付けをして惑わされる者と、幻影に囚われずに現実を見据える者の差が描かれた興味深い場面です。密林の中で何十年も一人で生き抜いてきた猟師のアニミズムには迷信など微塵も無く、徹底したリアリズムでもあったのです。
シーン21では、旧教徒の長老が、デルスが善人だと認めつつも、彼がアジア人でありキリスト教徒でないことが「悪い」ことだとして、こう言います「彼(デルス)には魂がなくて、たゞ息があるだけさ。それなのに、わしらと同じに生きておる」 この発言に対して、アルセーニエフは「私や、あんたと同じことですよ」と皮肉っぽく言います。
「クリスチャンでなければ人に非ず」とでも言いたげな旧教徒の言葉には、非常に傲慢なものを感じます。本当にキリスト教徒がそれほど人格者なのでしょうか。
脚本家の猪俣勝人が自ら監督した1959年の映画『殺されたスチュワーデス 白か黒か』は、同年発生したBOACスチュワーデス殺人事件を題材にした映画でした。日本人女性CA殺害の重要参考人であったベルギー人神父は状況証拠から真犯人の可能性が高かったにも関わらず、帰国していましました。映画の制作途中から公開に至るまでカソリック勢力による執拗な妨害があったそうです。
半世紀以上前はたった一人の聖職者による性犯罪と殺人事件でも社会的な衝撃でしたが、今では世界中でカソリック聖職者たちによるより大規模な性加害が明らかになってきました。もっとも、神父に限らず、日本でも僧侶や宮司による性加害が起きていますので、世界的な問題なのかもしれません。
そんなことを考えていますと、私自身の不快な過去を思い出してしまいました。
学生時代の私が絵を描く度に、北海道出身の同級生は、私の作品に対して「それはエゴだよ」と執拗に難癖をつけていました。
神父の息子だった彼の態度は、まるで自分の価値観に合わない絵は排除すべき異教徒だと言わんばかりの尊大なものでした。
そして、当時の私はまだ純情(笑)でしたので、自分の絵は間違っているのだろうかと少なからず悩んでしまいました。
ですが、卒業後、何度も個展を開催して、イラストレーターとしての活動を続けていく中で、私の作品を気に入ってくれる人達が増えてきました。そして、今では、間違っていたのは彼の方であり、私は間違っていなかったと断言できます。
勿論、芸術において何が正解かを定義するのは無意味かもしれませんが、他人の価値観を否定して自分の価値観を押し付けることこそ、邪悪な「エゴ」でしかありません。
話を『デルス・ウザーラ』に戻します。
「旧教徒の家」の場面も最終的にカットされましたが、実際に撮影されましたので、黒澤が重要な場面だと判断していた筈です。
黒澤は生涯、無宗教でしたので、同じ非キリスト教徒であり、アジア人でもあるデルス・ウザーラに自らを重ねていたとしても不思議ではありません。原作のアルセーニエフも、デルスと共に過ごす内に、ヨーロッパ人のみが人間的な美徳を持ち、野生の人間のみがエゴイスティックだという考えが誤りであったことに気付いていきます。(そう考えると、1961年の映画版『デルス・ウザーラ』は、ラストで、隊員の一人がデルスに十字架のネックレスをかけていたので、原作の精神に反するような気がします)
モノクロ時代の黒澤映画には宗教的な要素はほぼ皆無でした。カラー映画になってから宗教的な要素は徐々に出てきますが、重要なのは信仰が救いには結びついていないことです。
『どですかでん』では、六ちゃんの母親が毎朝お題目を唱えていますが、それが六ちゃんを「普通」にしないどころか親子の断絶を強調するのみです。『影武者』では武田信玄や上杉謙信が仏教に帰依していましたが、戦乱の世を変えることはありません。『乱』に至っては、仏教に救いを求めた末の方は無残に殺害され、弟の鶴丸は姉から貰った阿弥陀の仏画を落として、城跡でたった一人取り残されてしまいます。
因みに、美術史家のアレックス・セルツァー (Alex Seltzer) は、少年時代の黒澤は夭逝した姉・百代の葬式で笑い出したのに、『八月の狂詩曲』(1991) で村の老婆たちが般若心経を唱えるのを肯定的に描くのは矛盾していると指摘していました。美術史の博士号を持つセルツァーは、黒澤の自伝『蝦蟇の油』の記述から引用して、したり顔で批判できたと思ったかもしれませんが、重要な点を見誤っています。
先ず、少年時代の黒澤が笑ったのは、お経ではなかったことです。『蝦蟇の油』でも、彼が急に笑い出したのは、お経の合唱に木魚や銅鑼が加わって賑やかになったことでした。そして、百代の葬式と村人の供養とでは、お経の意味合いが異なります。百代の葬式は形式的な儀式であったのに対して、村人のお経は自発的に死者の冥福を祈る真摯なものであったのですから。
『七人の侍』や『デルス・ウザーラ』を賞賛しつつも、原爆投下を正当化するような歴史観のセルツァーは、同じお経でも形式的な儀式と心からの弔いの違いを見分けることもできなかったようです。
ともあれ、晩年の黒澤明は、『リア王』の結末に言及して、「神を頼んではいけない」「人間自体がもっとしっかりしなくてはいけない」と語っていました。(『エスクァイア日本版』1990年9月号) 迷信や宗教のように実態のないものではなく、森羅万象の生物や現象に等しく敬意を表し、卓越した洞察力で自然界を生き抜くデルス・ウザーラに、黒澤明が目指した最も理想的な人間の姿を見ることができます。
『デルス・ウザーラ』は「反中国」か
『デルス・ウザーラ』の映画化決定から公開までの1970年代前半は、冷戦とベトナム戦争の真っ只中でした。ブレジネフが最高指導者であった当時のソ連は中国とも険悪な関係にありました。
そうした政治的背景もあり、『デルス・ウザーラ』は中国やその支持者から「反中国映画」として批判されました。
又、当時の北米大統領ニクソンが中国を電撃訪問したことで米中が接近したせいか、ジョーン・メレンのように『デルス・ウザーラ』を「反中国プロパガンダ」として的外れな酷評をするアメリカ人批評家もいました。
井出雅人が『デルス・ウザーラ』の脚本執筆者の一人としてクレジットされるのを辞退したのも、当時、彼が日本中国友好協会の常任理事を務めていたため中国を刺激するの避けるための配慮でした。
黒澤と井出による第一稿を改訂したナギービンは、ソ連国家映画委員会からの指示もあり、反中国的な要素を強めようとしていました。ソ連側としては自国を正当化するためのプロパガンダとして、この映画を利用しようとしていたようです。
ですが、黒澤の映画『デルス・ウザーラ』は、それほど中国に対して批判的でしょうか?
『デルス・ウザーラ』の劇中で中国に批判的な箇所は、後半で描かれる乱獲や匪賊です。クライテリオンのレーザーディスクやモスフィルムの動画でも、匪賊を呼ぶデルスの台詞が英語字幕では「悪い中国人」と訳されていました。
デルスも匪賊の悪事には立腹していますが、劇中で描かれるのは乱獲の罠や匪賊に縛られた男たちであり、「悪い中国人」が画面上に登場することはありません。映画全体で見れば、前半で描かれる善良な老中国人リー・ツンビンの方が印象的だと思います。
「反中国映画」として見るなら、1961年の映画版『デルス・ウザーラ』の方が乱獲する中国人たちを悪人らしく描いていました。黒澤も同様の場面を撮影しましたが、フィルム不良や上映時間の制限という事情で欠番となっています。
アルセーニエフの探検記には、訪れた先々でウデヘ人が中国人によって残酷に搾取されている事例が数多く描写されています。ですが、同時に、善良な中国人もいて彼らに助けてもらったことも記されています。匪賊を討伐する正義漢ジャン・バオも中国人ですし。
黒澤明も『デルス・ウザーラ』で中国を誹謗する意図など無かったと明言していました。(『週刊プレイボーイ』1975年8月12日号)
モスクワ映画祭のモットーである「映画芸術におけるヒューマニズムと国家間の平和と友好のために」という立場で『デルス・ウザーラ』を撮った黒澤は、中国人を悪く描かせようとするソ連側に対して、ロシア人と中国人のどちらにも善人も悪人もいると反論したそうですし。(『〈デルスウ・ウザーラ〉製作記念特集・黒澤明ドキュメント』キネマ旬報増刊5・7号、1974年)
中国人による乱獲を批判したシーン62(欠番)でも、最後にデルスは「人、いろいろ。中国人も、いろいろ」と言っています。一部の無法者に対して批判的ではあっても、中国や中国人全体を否定している訳ではありません。
1974年3月15日、モスフィルムでのシナリオ打ち合わせでは、黒澤は「原住民を興味本位に、差別的に描きたくない」とも発言していました。
ただ、現在も中国政府はチベットや香港などに対して苛烈な抑圧を続けていますし、天安門事件のように自国民すら躊躇なく弾圧しています。このような非民主的な政策は決して許されるものではありません。
因みに、こうした中国政府の悪政を批判してきた日本の政党が日本共産党であったのに対して、与党である自民党や公明党はろくな批判もしない弱腰であったというのが何とも皮肉です。(「中国問題に日本共産党はどう対応してきたか/事実と道理で批判 打開の方策を提起」しんぶん赤旗 2021年7月1日)
それに、映画『デルス・ウザーラ』では描かれませんでしたが、原作によると、ジャン・バオは、1905年に彼の助手を殺害した日本人に対して仇討ちをした過去があるそうです。デルスも、ゴリド人やウデヘ人だけだった平和な土地に、中国人、ロシア人、朝鮮人が来たことにより生活が年々脅かされ、海岸には日本人まで来るようになったことに不安を覚えていました。
勿論、ソ連も国民に対して中国に劣らぬ恐怖政治を敷いていたことは言うまでもありません。
黒澤明が『デルス・ウザーラ』を撮っていた頃も、日本人スタッフの電話が盗聴されるなど常に当局に監視されていたそうです。
時代を遡って、スターリンによる大粛清は、アルセーニエフの家族さえも襲っていました。1919年、アルセーニエフはマルガリータと再婚して、娘ナターリヤも生まれました。ですが、彼の死後、地質委員会の研究員だったマルガリータは、1937年に「反政府活動」の疑いで逮捕され処刑されてしまいます。娘のナターリヤも1941年にグラーグ(強制収容所)へ10年もの刑を受け、1973年に死亡しました。先妻のアンナと息子のウラジーミルは、当時アルタイの森林管理所に住んでいたので無事でした。
後に都市に名前が付けられるほど英雄化されたアルセーニエフの家族が、いかにスターリニズムの時代とはいえ、このような酷い仕打ちを受けていたことに愕然とします。
そして、ソ連は崩壊しましたが、現在のプーチン政権はウクライナに対して軍事侵攻を続けていて、現在も犠牲者は増え続けています。
アメリカも原爆投下後、ベトナム戦争やイラク戦争などで多くの一般市民を虐殺しましたし、現在のトランプ政権は、パレスチナ人を虐殺し続けているイスラエルへの軍事支援をするなど暴政を敷いています。
日本も、今夏の参議院選挙で顕著だったように、デマやヘイトスピーチが蔓延するなど、外国人排斥が年々酷くなっています。
『デルス・ウザーラ』の公開から半世紀も経ちましたが、世界は相変わらず、国家間、民族間で戦争や殺戮を繰り返しています。この映画の公開後、黒澤が脚本執筆を始めた『乱』は、争いを止めない人間の愚かさを描いた大作でした。
乱獲や悪質な商売をする者に対しては、デルスも辛辣な言葉で怒りを露わにします。ですが、基本的に、デルスは誰に対しても分け隔てなく接していました。黒澤の映画『デルス・ウザーラ』は、一部の人が言うような「反中国プロパガンダ」などでは断じてないと思います。
アルセーニエフがデルスと出会って間もない頃、中国人が夜を明かした後の無人の小屋に、デルスは米と塩とマッチを残していきます。後で誰かが小屋に辿り着いたときに、飢え死にしないようにするためでした。恐らく会うこともないであろう他人への配慮も忘れないその優しさに、アルセーニエフは心を打たれます。
原作でも、ジギト湾のほとりで、デルスは運んできた肉を三等分して、ロシア兵、旧信徒、近所の中国人に分配しました。抗議する兵士に対して、デルスは「ひとりでみんなとる、わるい」と反論しました。アルセーニエフは、デルスが自分の獲物を常に「民族を問わず、隣人みなに等分に与え、自分はそれと同じ分け前をとった」と書いています。
勿論、現代の世知辛い文明社会で果たしてどこまでデルスのような博愛主義を貫けるのか心許なくなります。ですが、根拠もない情報に惑わされて排外主義に飛びつくような軽挙妄動が流行っている今こそ、『デルス・ウザーラ』の美しい精神は一服の清涼剤だと思います。
黒澤明は「西洋的」か「東洋的」か
モノクロ映画の頃から黒澤映画は、良くも悪くも「西洋的」と形容されることが多かったようです。
確かに、『羅生門』の一部の曲はラヴェルの《ボレロ》にしていましたし、西部劇風の活劇を狙った『七人の侍』や『用心棒』は、ハリウッドで西部劇にリメイクされましたし、ドストエフスキーやシェイクスピアなど西洋の文学を何度も映画化したことも黒澤が「西洋的」と思われた要因でした。
ですが、黒澤は、西洋の文学やクラシック音楽などを愛好していたのと同時に、能や俳句など自国の伝統文化にも造詣が深かったです。
考えてみれば、日本という国そのものが、明治時代の文明開化より遥か以前の遣隋使・遣唐使の頃から、海外の文化を取り入れて自己流に「改善」することを繰り返し行ってきました。
拙ブログでも過去に検証したように、ドストエフスキーの小説を映画化した『白痴』、ダシール・ハメットの『血の収穫』を下敷きにした『用心棒』、シェイクスピア戯曲を翻案した『蜘蛛巣城』(1957) と『乱』のように西洋の素材を題材にしたときも、黒澤映画には日本的な要素が満ちていました。
そして、黒澤映画を海外でリメイクした映画と比較すると、更に黒澤の日本的な要素が引き立つと思います。
井出雅人も「黒澤をヨーロッパ好みなどとは錯覚も甚だしい。純粋に日本人の思想と感性を備えているから、世界で受け入れられるのだ」と書いています。(『シナリオ』1985年9月号)
ソ連で映画を撮る企画が持ち上がった際、ドストエフスキーの『死の家の記録』やゴーゴリの『隊長ブーリバ』が候補に上がりましたが、最終的には黒澤が提案した『デルス・ウザーラ』が選ばれました。助監督時代に読んで感銘を受けて、敗戦後に日本で一度映画化を試みて頓挫して以来、約30年ぶりに他ならぬ原作の舞台となった国で映画化できるという僥倖は、それだけでも映画的です。それに、ソ連映画とは言え、主人公のデルス・ウザーラはゴリド人(ナナイ)というアジア人です。
デルスを演じたマクシーム・ムンズークは、トゥヴァ共和国の俳優でした。黒澤と同じ1910年生まれのムンズークは、デルスのように狩りもする生活をしていました。彼が猟師役で出演したモスフィルムの映画『失われた証人』(1971) の試写を見た黒澤は、デルスによく似たムンズークをすぐに気に入りました。
デルス役に選ばれたムンズークでしたが、主に舞台で活躍していましたので、最初は映画向きの自然な演技がなかなかできずに苦労したそうです。ですが、黒澤やソローミンの演技指導の甲斐もあって、完成した映画ではそうした苦労を感じさせないほど、デルスを自然に演じ切っていました。
余談ですが、快楽亭ブラック(二代目)は、三船敏郎と決別した後の黒澤のカラー映画を全否定していて、三船主演であればカラーの黒澤映画も「少しは見られた映画になっていたんじゃあないだろうか」などと書いています。(『生誕100年総特集 黒澤明〈増補新版〉』河出書房新社) 同じように、晩年の黒澤映画に三船主演を望む人は少なくありません。
ですが、セクハラ落語家の暴論など、私に言わせれば「分かってないなぁ」でしかありません。三船主演の『デルス・ウザーラ』など、三船主演の『影武者』や『乱』以上に有り得ないと思います。
三船プロの社長でもあった三船には1年以上もの海外ロケが不可能という現実的な理由は勿論ですが、何よりも役に合っていません。東北のマタギならまだしも、自然の森羅万象と対等に生きて、善良な心を体現した自然人のナナイ人猟師の役はムンズーク以外には考えられません。(ただ、製作発表で三船起用の可能性をほのめかした黒澤のリップサービスを真に受けてしまい出演のために奔走してしまった三船には同情しますが)
閑話休題。
地理的にも、アルセーニエフが探検した沿海州は、日本海を挟んで北海道の目と鼻の先です。そして、映画前半の見せ場となるハンカ湖は、中国とロシアの国境地帯にある淡水湖です。沿海地方は中国の国境沿いに位置していますので、ウデヘ人などの先住民の他にも中国人や朝鮮人の移住者が多数住んでいることがアルセーニエフの探検記に記されています。
何よりも、映画『デルス・ウザーラ』全体の雰囲気が、非常に「東洋的」です。脚本改訂や困難なロケの過程を経て、自然に合わせて撮っていくことによって、当初の活劇的な要素は薄まり、自然の中で生きる人間の卑小な存在と、デルスの美しい精神がより際立ちました。イサク・シュヴァルツによる見事な音楽も、西洋的というより東洋的な静謐さで、主張し過ぎず画面に寄り添っていました。
黒澤の全作品中、唯一の外国語映画となった『デルス・ウザーラ』が、日本で撮られた黒澤映画よりも東洋的な作品となったのは、様々な要因から結果的にそうなった面もあるかもしれません。ですが、外国に行った人なら誰もが自分のアイデンティティを意識するように、異国の地で異邦人として撮っていた黒澤が、日本にいたとき以上に日本人である自分を意識したとしても不思議ではありません。
サタジット・レイは、ジャン・ルノワールがアメリカで撮った『南部の人』(1945) やインドで撮った『河』(1951) がルノワールのフランス映画以上に彼の「フランスらしさ」が出ていると書いていました。同様に、黒澤明についても「西洋の影響を受けているにもかかわらず、私たちの考える以上に、根は日本的なのかもしれない」と書いていました。(『わが映画インドに始まる 世界シネマへの旅』第三文明社)
黒澤も、自伝の中で、日本で映画を撮れなくなった自分を鮭に例えて、ソ連でキャビア(『デルス・ウザーラ』)を生んでも、やはり日本で撮りたい心境を綴っていました。
黒澤明が苦闘の末に完成させた映画『デルス・ウザーラ』は、物語の内容も、作品の雰囲気も、東洋や西洋という垣根を超越して、公開から半世紀を経た今も、地球上の全ての人類に爽やかな感動を与え続けている珠玉の名作だと思います。
(敬称略)
参考資料(随時更新)
書籍
『世界映画名作全史〈現代編〉』 猪俣勝人、現代教養文庫、1975年
Eder, Richard. “Contrasts Evident in Japanese-Soviet Movie.” The New York Times, October 5, 1976.
『日本映画作家全史(上)』 猪俣勝人、田山力哉、現代教養文庫、1978年
『ハリウッド映画特急 L.A.EXPRESS』 原田眞人、早川書房、1986年
『巨匠のメチエ 黒澤明とスタッフたち』 西村雄一郎、フィルムアート社、1987年
『全集 黒澤明 第六巻』 黒澤明、岩波書店、1988年
『黒澤明 集成』 キネマ旬報社、1989年
『黒澤明 集成Ⅱ』 キネマ旬報社、1991年
『巨人と少年 黒澤明の女性たち』 尾形敏朗、文藝春秋、1992年
Setzer, Alex. “Akira Kurosawa: Seeing Through the Eyes of the Audience.” Film Comment, May-June 1993.
『黒澤明 集成Ⅲ』 キネマ旬報社、1993年
『わが映画インドに始まる 世界シネマへの旅』 サタジット・レイ 著、森本素世子 訳、第三文明社、1993年
『異説・黒澤明』 文藝春秋、1994年
『デルスー・ウザーラ 上』 ウラジーミル・アルセーニエフ 著、長谷川四郎 訳、河出書房新社、1995年
『デルスー・ウザーラ 下』 ウラジーミル・アルセーニエフ 著、長谷川四郎 訳、河出書房新社、1995年
『キネマ旬報 復刻シリーズ 黒澤明コレクション』 キネマ旬報社、1997年
『黒澤明 音と映像』 西村雄一郎、立風書房、1998年
『村木与四郎の映画美術 [聞き書き]黒澤映画のデザイン』 丹野達弥 編、フィルムアート社、1998年
『評伝 黒澤明』 堀川弘通、毎日新聞社、2000年
『蝦蟇の油 自伝のようなもの』 黒澤明、岩波書店、2001年
『黒澤明の食卓』 黒澤和子、小学館、2001年
『黒澤明 天才の苦悩と創造』 野上照代 編、キネマ旬報社、2001年
『黒澤明を語る人々』 黒澤明研究会 編、朝日ソノラマ、2004年
『黒澤明VS.ハリウッド 『トラ・トラ・トラ!』その謎のすべて』 田草川弘、文藝春秋、2006年
『黒澤明 封印された十年』 西村雄一郎、新潮社、2007年
『大系 黒澤明 第2巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2009年
『大系 黒澤明 第3巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2010年
『大系 黒澤明 第4巻』黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2010年
『生誕100年総特集 黒澤明〈増補新版〉』 西口徹 編、河出書房新社、2010年
『もう一度 天気待ち 監督・黒澤明とともに』 野上照代、草思社、2014年
『黒澤明と「デルス・ウザーラ」』 ウラジーミル・ワシリーエフ 著、池田正弘 訳、東洋書店、2015年
『黒澤明 樹海の迷宮 映画「デルス・ウザーラ」全記録1971~1975』 野上照代、ヴラジーミル・ヴァシーリエフ、笹井隆男、小学館、2015年
『旅する黒澤明 槙田寿文ポスター・コレクションより』 国立映画アーカイブ 監修、国書刊行会、2020年
映像・音声媒体
LD, Dersu Uzala. The Voyager Company (The Criterion Collection), 1995.
CD『デルス・ウザーラ』 イサク・シュワルツ、東宝ミュージック、AK-0011、2002年
DVD『デルス・ウザーラ』 アイ・ヴィー・シー、2000年
DVD『デルス・ウザーラ』 東宝株式会社、2002年
DVD『黒澤明 創造の軌跡 黒澤明 “THE MASTERWORKS” 補完映像集』 東宝株式会社 映像事業部、2003年
DVD『デルス・ウザーラ』 オデッサ・エンタテインメント、2013年
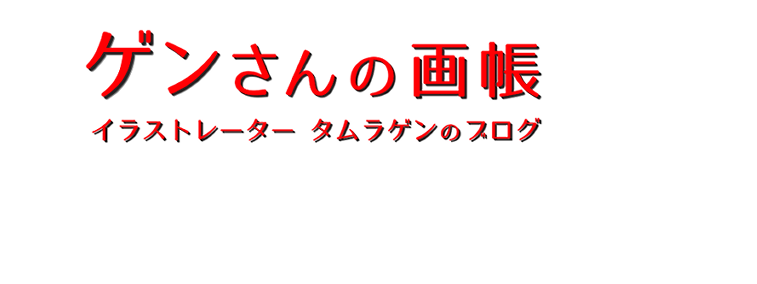
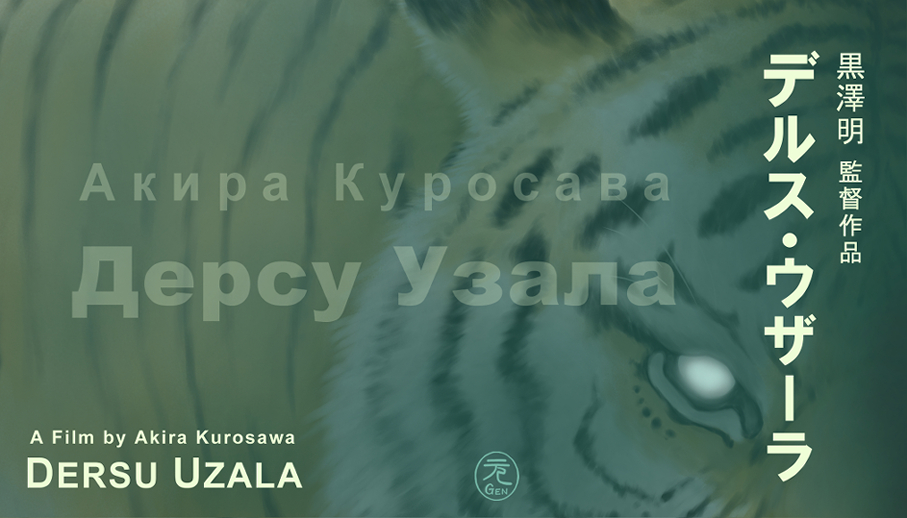













コメント