こんにちは。タムラゲン (@GenSan_Art) です。
30年前の今日 (5月25日) は、黒澤明の映画『夢』(1990) が公開された日です。黒澤自身が見た夢を題材にした8つの短編から成るオムニバス映画です。
『夢』について
夢
Akira Kurosawa’s Dreams
1990年5月25日 日本公開
黒澤プロダクション 製作
ワーナー・ブラザーズ 配給
カラー、ビスタビジョンサイズ、119分
スタッフ
監督・脚本:黒澤明
提供:スティーブン・スピルバーグ
プロデューサー:黒澤久雄、井上芳男
アソシエイト・プロデューサー:アラン・H・リーバート、飯泉征吉
プロダクション・マネージャー:野上照代
プロダクション・コーディネーター:末弘厳彦
演出補佐:本多猪四郎
撮影:斎藤孝雄、上田正治
撮影協力:原一民
美術:村木与四郎、櫻木晶
照明:佐野武治
録音:紅谷愃一
効果:三縄一郎、斎藤昌利
衣装デザイナー:ワダエミ
装飾小道具:浜村幸一
音楽:池辺晋一郎
助監督:小泉堯史
振付:畑道代
ピアノ演奏:遠藤郁子
題字:今井凌雪 (雪心会)
特撮・合成技術協力:INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC (A Lucasfilm Ltd.)、SONY
助監督:米田興弘、酒井直人、杉野剛、早野清治、田中徹、ヴィットリオ・ダッレ・オーレ
視覚効果スーパーバイザー:ケン・ラルストン、マーク・サリバン
キャスト
第1話「日照り雨」
5歳位の私:中野聡彦
私の母:倍賞美津子
狐の嫁入り:舞踊集団菊の会
第2話「桃畑」
少年の私 – 伊崎充則
桃の精 – 建みさと
姉 – 鈴木美恵
雛人形達 – 二十騎の会
第3話「雪あらし」
私 (第3話~第8話):寺尾聰
雪女:原田美枝子
パーティの仲間:油井昌由樹
パーティの仲間:中嶋しゅう
パーティの仲間:木村栄
第4話「トンネル」
野口一等兵:頭師佳孝
少尉:山下哲生
第三小隊:二十騎の会
第5話「鴉」
フィンセント・ファン・ゴッホ:マーティン・スコセッシ
洗濯女:カトリーヌ・カドゥ
第6話「赤冨士」
発電所の男:井川比佐志
子供を抱えた女:根岸季衣
第7話「鬼哭」
鬼:いかりや長介
鬼達:二十騎の会
第8話「水車のある村」
103歳の老人:笠智衆
村人:木田三千雄
村人:常田富士男
村人:七尾伶子
村人:本間文子
村人:東郷晴子
村の踊る娘たち:舞踊集団菊の会
予告篇
個人的鑑賞記
公開当時から賛否が別れる『夢』ですが、個人的にとても好きな映画です。
「日照り雨」と「桃畑」の美しさや、「トンネル」の哀惜、「鴉」の奇想天外な楽しさ、「水車のある村」の純朴さは何度見ても心が洗われる素晴らしさです。
よく指摘される冗長な場面や説教的な台詞という欠点を差し引いても、この映画は捨てがたい魅力に満ちています。
因みに、『夢』は、私がリアルタイムで観た最初の黒澤映画でもあります。
1988年頃、レンタルビデオで『用心棒』(1961) や『椿三十郎』(1962) 等を見て以来、黒澤映画に夢中になっていましたので、『乱』(1985) から5年ぶりの新作を心待ちにしていました。
劇場 (グランド松竹)
1990年5月に香川県高松市のグランド松竹で公開されたときは喜び勇んで観に行きました。
「白黒時代に比べてカラーになってからの黒澤映画はつまらなくなった」という批判もありましたが、『影武者』(1980) や『乱』も白黒時代とは異なる独自の魅力があると思っていましたので、より映像美が際立った『夢』をスクリーンで堪能しました。当時の映画館は入れ替え制ではなかったので、1日に3回連続で居続けるなどして、10回は映画館で鑑賞しました。
あれから、もう30年。黒澤明をはじめ、本多猪四郎、斎藤孝雄、村木与四郎など主なスタッフは世を去りました。高松市の映画館も、グランド松竹を含めてシネコン以外の映画館は殆ど全て姿を消しました。映画はフィルム上映からデジタル上映が主流になり、映像ソフトもVHSやLDからDVDやBlu-rayに移り変わり、今ではネット配信で新旧の映画をより手軽に見れるようになりました。
80年代が終わり90年代に入ったときは新時代が到来したかのような錯覚を覚えましたが、こうして振り返ると、月日の流れの早さとテクノロジーの変換を痛感します。
Blu-ray (クライテリオン・コレクション)
2016年、アメリカのクライテリオン・コレクション (The Criterion Collection) から『夢』のBlu-rayが発売されました。キャメラマン上田正治の監修によってデジタル修復された4K映像は、期待通りの高画質でした。ただ、「日照り雨」や「雪あらし」が少し緑っぽい色調なのが気になりました。ですが、『乱』4Kの青すぎる映像に比べれば遥かに許容範囲内です。
映像特典も非常に充実しています。予告篇の他に、大林宣彦によるメイキング映像『映画の肖像 黒澤明 大林宣彦 映画的対話』(1990) と、カトリーヌ・カドゥのドキュメンタリー『黒澤 その道』(2011)、野上照代と小泉堯史の撮り下ろしインタビューなど、盛り沢山です。
ところで、ワーナーから発売中のDVDは、日本版も冒頭と結末のタイトルが英語表記になっていますが、クライテリオンのソフトでは日本公開時と同じく今井凌雪による日本語タイトルで収録されています。
各エピソードについて
日照り雨
あらすじ
武家屋敷のような家に住む幼い「私」。降り出した日照り雨を見て母親は、狐の嫁入りを見ると恐ろしいことになるので出ていかないよう「私」に忠告します。ですが、「私」は林の中で狐の嫁入りに遭遇し、狐たちに見付かってしまいます。「私」は慌てて帰宅しますが、母親から短刀を渡され、死ぬ気で狐に許しを請わない限り戻ってはならないと言われ門を閉ざされてしまいます。山並みの上にかかった虹を不安そうに見ながら「私」は虹に向かって歩いていきます。
黒澤明の自伝的世界
題名が示すように、『夢』は、黒澤明が実際に見た夢を黒澤が自ら脚色して映像化した8つの短編から成る映画です。
黒澤映画としては珍しいオムニバス形式です。夢という性質上、短い話の方がしっくり来ると思います。黒澤の娘・和子によると、80歳を目前にした黒澤が時間が無いと感じたことも、幾つもの話を同時に撮りたくなった動機だそうです。
この映画を見た人の中には、日照り雨の中を「私」が傘もささずに出歩くことや、ファン・ゴッホが英語を喋ることや、放射能の着色が有り得ないなどと苦言を呈する人もいました。ですが、この映画が黒澤の見た夢の世界である以上、そうした「リアルでない」という指摘が全く無意味であるのは言うまでもありません。
過去の黒澤映画は、巨大な城門や噴水のような血飛沫など誇張した表現が賛否両論を巻き起こしましたが、夢の世界は現実離れした表現こそあるがままに楽しむべきでしょう。
それに、狐の嫁入りや次の「桃畑」も、黒澤の撮り方は非常に上品で、御伽話のような世界に違和感なく観客を誘ってくれます。
又、幼い「私」が住む屋敷の門に「黒澤」の表札がかかっているように、『夢』には黒澤自身の過去モデルにした自伝的要素もかなり含まれています。
スティーヴン・プリンスは、Blu-rayのコメンタリーで、「日照り雨」の神話的雰囲気が雄大である一方、幼少期の私が渡される短刀が、黒澤の兄・丙午の自殺と黒澤自身の自殺未遂という黒澤家の暗い過去も暗示していると指摘していました。
桃畑
あらすじ
雛人形が飾られている座敷で、少年の「私」は、姉を含めた5人の少女に団子を配りに来ます。「私」は、桃の花の傍に、少女達には見えない不思議な少女を見付けます。少女を追って段畑に来た「私」の前に、等身大の雛人形の一団が出現します。桃の木を切ったことを非難する雛人形達に対して、「私」は好きだった桃畑が切られることが悲しかったことを涙ながらに訴えます。その気持ちに打たれた雛人形達は、壮麗な舞を「私」に披露します。舞い終えた雛人形達は姿を消し、元の伐採された段畑に戻ります。「私」の前には、僅かな花を咲かせていた小さな桃の木が一本だけ残されていました。
黒澤明の映像美
雛人形の一団による舞が圧巻の一編です。この場面が見たくて何度も映画館に通いました。
音楽も素晴らしいです。『影武者』以降、クラシック音楽を具体例として作曲家に提示する黒澤の無理難題な要求に、池辺晋一郎は見事に応えていると思います。雅楽が流れる舞の後に桃の木が蘇る映像には、パッヘルベルの《カノン》が付けられていたそうですが、池辺はオルガンを中心とした美しい曲に巧みに換骨奪胎していました。
このエピソードには多言は無用だと思いますので、実際にその映像美を体験して頂くのが一番です。
雪あらし
あらすじ
遭難した4人の登山者が雪渓を彷徨っています。憔悴しきった彼等を吹雪が襲い、「私」以外の3人は気を失ってしまいます。「私」も意識が薄れていく中、雪女が現れます。雪女の歌と衣で眠りに落ちそうになりますが、必死でそれを振り払うと雪女は恐ろしい形相に変化して空に消えていきました。吹雪が止み、陽が射してくると、目を覚ました登山者達は、近くに雪に埋もれたアタック・キャンプがあるのを発見するのでした。
黒澤明の雪女
御伽話のような最初の二話から一転、大人の「私」が過酷な大自然の中で生死の境をさ迷うエピソードです。
最初の約3分間は、遭難した登山者が力無く彷徨う様子を、台詞無しで延々と見せていきます。普通なら長すぎると感じてしまう所ですが、この執拗な描写だからこそ雪山で行く先も分からず疲弊し朦朧としていく感覚を観客も共有できるとも言えます。
因みに、こうした観客を麻痺させる長い描写は、過去の黒澤映画でも時々ありました。『野良犬』(1949) で復員兵に変装した刑事が闇市を徘徊する場面や、『羅生門』(1950) で杣売りが森の中を歩いていく場面、『蜘蛛巣城』(1957) で二人の騎馬武者が霧の中をさ迷う場面、『デルス・ウザーラ』(1975) の吹雪の中で草を刈り続ける場面、『影武者』のラストで討たれた大勢の騎馬武者、といった具合です。
雪女の出てくる映画となると、やはり小林正樹の『怪談』(1965) の第2話「雪女」を連想してしまいます。小林の雪女が小泉八雲の原作の映画化であったのに対して、黒澤の雪女はオリジナルのストーリーで現代が舞台です。
どちらもセットで吹雪を再現していますが、『怪談』が全編様式美を強調していたのに対して、『夢』の雪山は大自然の過酷さをより強調していました。その撮影は、この映画に山岳アドバイザーとして参加した日本山岳協会・海外委員長の神崎忠男も「本物の雪山よりも、雪山ですよ」と驚いたほど大掛かりだったそうです。登山者の疲労困憊した様子を描写していたからこそ、薄れゆく意識の中で現れる雪女の幻想的な雰囲気が際立っていました。
「雪あらし」は、遭難の描写を冗長と感じるかどうかで評価は分かれそうです。それでも、メッセージ性が濃くなる後半と比べれば、台詞も少ないですし、夢と現実の境界線が曖昧なまま終わる点が夢らしいと思います。
トンネル
あらすじ
軍服を着た「私」が、夕暮れの道の途中にあるトンネルに差し掛かります。その入口で、爆弾を背負った軍用犬に威嚇されながらも、トンネルを通り抜けます。その直後、戦時中に部下だった一等兵と小隊の亡霊に遭遇します。彼等を戦死させて自分だけ生き残ってしまったことを「私」は真摯に謝罪して、亡霊をトンネルの暗闇へと送り返します。泣き崩れる「私」の前に、再び異様な軍用犬が現れ彼に咆哮し続けるのでした。
黒澤明と戦争
「トンネル」は、黒澤映画としては珍しく第二次世界大戦に直接絡んだエピソードです。
戦後間もない頃の黒澤映画にも戦争が影を落としますが、『わが青春に悔なし』(1946) では真珠湾攻撃のラジオ放送からすぐに戦後に飛びますし、『静かなる決闘』(1949) の冒頭では主人公の軍医が南方の野戦病院で手術をする場面がありますが、すぐに戦後の日本が舞台に移りますし、『野良犬』(1949) は主人公の刑事と犯人が元復員兵でしたが、これも舞台は当時の現代です。戦時中に撮られた『一番美しく』(1944) でさえレンズ工場が舞台で、実際の戦闘は描かれません。
戦前・戦時中、多くの映画人が次々と召集され、戦地に散った命も少なくありませんでした。1930年、黒澤明も20歳のときに召集されましたが、徴兵司令官が陸軍体育教官だった黒澤の父・勇の教え子であったので兵役を免除されました。東宝の前身であったP.C.L.に入社後も、助監督仲間であった本多猪四郎が何度も召集されたのとは対照的に、黒澤は一度も兵役に就くことなく敗戦を迎えました。
徴兵を免れたことが黒澤にとって幸運であったのは間違いないですが、戦場を実体験しなかったが故に、多くの同胞が命を奪われた戦争を描くことを躊躇するようになったようです。
自伝『蝦蟇の油』でも、戦時中には軍国主義に無抵抗で、時流に迎合したり逃避していたため、戦争中のことを批判する資格が自分には無いと書いていたほどです。
普通なら、時代劇やSFのように実際に体験しなかったことを映画で描いてもおかしくありませんが、夥しい犠牲者を出した第二次世界大戦は時代が近く体験者が多かったため、黒澤と言えども手を出しにくかったのかもしれません。
その黒澤が戦争を題材に撮ったエピソードは、80歳近くになった彼が戦争について思うことを後世に残そうとする遺書のようにも見えます。(『影武者』がパルム・ドールを受賞したカンヌ国際映画祭での記者会見でも、黒澤は「どんな作品を作る場合も、遺言のつもりで作っています」と答えていました。)
『影武者』の長篠の戦いの間接描写もそうでしたが、「トンネル」も戦場を直接描くことなく戦争の虚しさを表現している点が出色でした。トンネルの長い暗闇は、満州事変から敗戦に至るまでの悪夢のようですし、最後に再び姿を現す不気味な軍用犬も、日本が軍国主義の負の遺産を今も清算できていない暗示のように見えます。
「トンネル」は、『夢』の中でも傑出したエピソードだと思います。
鴉
あらすじ
美術館でファン・ゴッホの絵画を鑑賞していた「私」は、『アルルの跳ね橋』の中に入っていきます。「私」がオーヴェル・シュル・オワーズの風景を歩いていると、草地で熱心にスケッチしているファン・ゴッホに出会います。絵について熱く語ったファン・ゴッホは時間を惜しむかのように姿を消します。「私」はファン・ゴッホを探し求め、その絵の世界を彷徨います。
黒澤明とファン・ゴッホ
映画監督になる前の黒澤明が画家志望であったことはよく知られています。青年時代にセザンヌやファン・ゴッホに傾倒していた黒澤が尊敬する画家の夢を見て、それを映像化するのは必然だったのかもしれません。
ファン・ゴッホを演じるのは、マーティン・スコセッシ。『タクシー・ドライバー』(1976) や『レイジング・ブル』(1980) などで既に著名な映画監督だったスコセッシが黒澤映画に出演するとは中々大胆な配役です。この映画の数年前、カラーフィルムの退色防止の運動をしていたスコセッシが、ニューヨーク滞在中の黒澤に会って、熱心に協力を呼びかけました。そのときのスコセッシのエネルギッシュな印象が黒澤の中でファン・ゴッホのイメージと結び付いたそうです。
『アルルの跳ね橋』の洗濯女とはフランス語で会話していたのに、ファン・ゴッホがニューヨーク訛りの英語で喋りだすことに面喰った外国人は少なくなかったようです。事実、私がアメリカの映画館で鑑賞したときも、スコセッシが英語で喋りだした途端、客席から困惑の混じった苦笑が漏れていました。
言語の他にも、ファン・ゴッホの耳切り事件も、映画では耳が上手く描けなかったからという理由で自ら切り落としたと言っていますが、事件の原因と経緯については諸説あり現在でも不可解な点が多いです。
もっとも、言語や耳が史実と異なるとは言っても、この映画そのものが黒澤明が見た夢を映像化した世界ですので、史実に忠実なファン・ゴッホではなく黒澤のイメージしたファン・ゴッホであっても不自然ではありません。
『蝦蟇の油』に、黒澤明は自分が癲癇持ちであることを書いています。偶然の一致かもしれませんが、黒澤が敬愛するドストエフスキーとファン・ゴッホも癲癇持ちだと言われていますので、その個性的な表現は何処か相通じるものがあったのでしょうか。ファン・ゴッホの独特の色彩と黒澤の強烈な絵コンテのタッチは確かに似ていると言えば似ているかもしれません。
奇しくも、『夢』が公開された1990年は、ファン・ゴッホの没後100周年でした。
劇中のファン・ゴッホの作品
「鴉」に登場したフィンセント・ファン・ゴッホ (1853-1890) の作品を画面に登場する順に並べてみました。1888年から1890年の間にオーヴェル・シュル・オワーズで描いた作品が選ばれているのが分かります。
| 題名 | 制作年 | 所蔵場所 |
| 自画像 | 1889 | ナショナル・ギャラリー(ワシントン D.C.) |
| 星月夜 | 1889 | ニューヨーク近代美術館 |
| ひまわり | 1888 | ノイエ・ピナコティーク(ミュンヘン) |
| カラスのいる麦畑 | 1890 | ファン・ゴッホ美術館 |
| ファン・ゴッホの椅子 | 1888 | ナショナル・ギャラリー(ロンドン) |
| アルルの跳ね橋 | 1888 | クレラー・ミュラー美術館 |
| ファン・ゴッホの寝室 | 1888 | ファン・ゴッホ美術館 |
| タラスコンへの道 | 1888 | ソロモン・R・グッゲンハイム美術館 |
| サント・マリーの通り | 1888 | メトロポリタン美術館ファン・ゴッホ美術館 |
| 家々のある風景 | 1890 | ファン・ゴッホ美術館 |
| わらぶき屋根の家 | 1890 | オルセー美術館 |
| 糸杉と星の見える道 | 1890 | クレラー・ミュラー美術館 |
| 花咲く庭と小道 | 1888 | ハーグ美術館 |
| 道路工事 | 1889 | フィリップス・コレクション(ワシントン D.C.) |
| 背景に馬車と列車のある風景 | 1890 | プーシキン美術館 |
| 糸杉のある小麦畑 | 1889 | ナショナル・ギャラリー(ロンドン) |
赤富士
あらすじ
富士山の近くにある原子力発電所が事故を起こして次々と爆発します。その炎で富士山が真っ赤になり溶けていきます。逃げ惑った大勢の群衆も海に身を投げてしまいました。断崖絶壁に残された「私」と原発職員と幼子を連れた母親の前に、放射能が迫ってきます。
黒澤明の反核
「赤富士」は、3.11以降『夢』が再び注目されるキッカケとなったエピソードです。
富士山の背後で次々と大爆発する原発は、2011年の東日本大震災で発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を予見したかのような映像で、改めて慄然とします。
黒澤明は、核(核兵器と原子力発電の両方)に強く反対していました。『生きものの記録』(1955) では原水爆と放射能の脅威に無関心な日本人を描き、『夢』の次作『八月の狂詩曲』(1991) では長崎に投下された原爆の被爆者を描いていました。1986年にチェルノブイリ原発事故があったとは言え、80年代の後半に原発を真正面から批判する映画を撮った黒澤の気概と先見の明には感服します。
そう言えば、2011年3月3日、私はこのようなツイートを投稿していました。
黒澤明の『夢』(1990)の第6話「赤富士」には考えさせられる。原発の爆発が富士山を溶かし、日本が滅亡してしまう。これを「荒唐無稽」だと嗤うのは簡単だが、実際に原発事故が起きた際、具体的に誰が責任を取れるのだろうか?やはり日本人は日本列島から逃げられず放射能に怯えるだけなのか。
— タムラゲン Gen Tamura (@GenSan_Art) March 3, 2011
このツイートから僅か1週間後に原発爆発という悪夢が正夢になるとは夢にも思いませんでした。
原子炉の爆発のみならず、映画と同種の放射性物質(プルトニウム239、ストロンチウム90、セシウム137)による汚染まで現実となってしまいました。
もはや、この悪夢を「荒唐無稽」と笑うことは出来ない現実に私達は生きています。
スティーヴン・プリンスがBlu-rayのコメンタリーで、このエピソードを “Post Fukushima” と比較するのは必然的としながらも、”apocalyptic” (黙示録の、世界の終わり的) なことは何も起きなかったと、原発事故が大したことではなかったかのように語っていたのには失望しました。
プリンスのコメンタリーは優れてはいますが、この点に関しては同意しかねます。(ついでに言えば、『生きものの記録』の主人公が核戦争から逃れるための移住先をプリンスはオーストラリアと言っていますが、正確には南米です。)
確かに、映画のように富士山が溶けたり日本人全員が全滅するほどではなかったにしても、チェルノブイリ原発事故と同じレベル7のメルトダウンによって、大量の放射性物質が撒き散らされ、数万人もの住民が故郷と生活を奪われ、絶望して自ら命を絶った人も少なくありません。しかも、9年以上経った今も原子力緊急事態宣言は解除されていません。これが大惨事でなくて何だと言うのでしょう。
『夢』の原発批判に対して「映画を撮るのにも原発の電気が必要だ」という声もありました。ですが、日本国内の電力は火力発電が主流で、原発が無くても電気は足りることは原発事故後に国内の原発が全て停止しても電力供給に何の問題も無かったことで実証されています。
又、原発推進派は「火力に依存すると石油が云々」と言いますが、原発も建設・廃炉・燃料の採掘と精製・核のゴミ処理などで石油を消費しています。その上、それらの過程でCO2も出すので温暖化対策にもなりません。何より増え続ける放射性廃棄物は今も完全な処理方法が見いだせない有り様です。
そして、原発は安くもありません。推進派は「国富の流出」とか「燃料費が高い」などと火力発電を目の敵にしていますが、原発こそ事故の賠償は勿論、核のゴミ処理や廃炉費、巨額の広告費も含めれば、火力よりコストが高すぎて経済的にも割に合いません。
要するに、原発は電力、環境、経済など全ての面で無用の長物なのです。
こうした原発批判を「ゼロリスク信仰」と揶揄する人もいますが、3.11前は「絶対に事故は起こらない」「原発は安い」などと安全神話で地元住民や消費者を騙しておきながら、東電の原発事故後は被害者を中傷したり詭弁を弄して責任逃れをする卑怯な原発容認派に反対派を批判する資格などありません。
東電原発のメルトダウンから9年以上が過ぎましたが、まだ核燃料は取り出せず、汚染水は増える一方で、数万人もの被害者は故郷を奪われたままです。史上最悪級の原発事故を起こしても被害者への賠償を渋る東電の責任者は誰も逮捕されないというのは不条理としか言いようがないです。
廃炉が決まった福島第一原発の4基を除いても、日本中にまだ50基もの原発が残っています。他の原発の避難計画も杜撰なまま再稼働を強行しようとする動きが絶えません。
その上、原発事故の被害者への賠償も不十分な中、汚染度を全国へ拡散しようとする愚行まで進められています。
富士山の噴火や南海トラフ大地震などの危険性が指摘されているのですから、一刻も早く全ての原発を廃炉にするべきです。
原発震災の悪夢を繰り返してはなりません。
反原発メモ
『報道ステーション』(2013年9月20日放送) 「〝現代人への伝言〟 黒澤明 没後15年」文字起こし
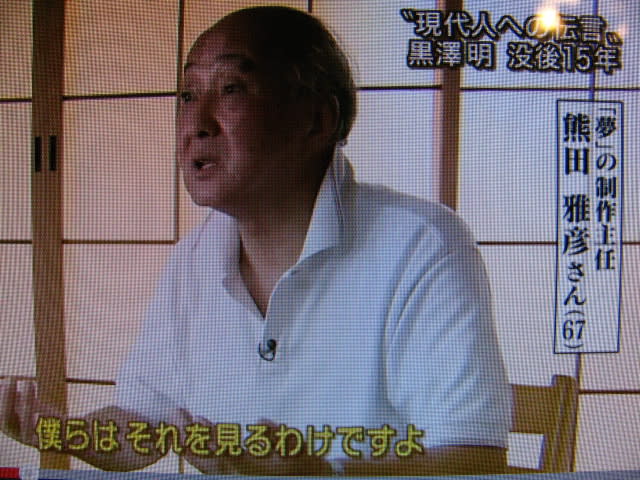


「原発問題 全般」
「原発は安くない」
「原発と石油」
「原発は温暖化対策にはならない(原発も二酸化炭素を排出する)」
「東京電力福島第一原子力発電所事故の放射能汚染による被曝症状」
「御用学者」
「原発とメディア」
鬼哭
あらすじ
核戦争で生物が死に絶え荒廃した世界。そこを一人で歩いていた「私」は1匹の鬼に出会います。鬼も以前は人間でしたが、核兵器の放射能で角が生えたのです。血のように真っ赤な池のほとりには、角が複数生えた鬼が大勢いて、角の痛みにもがき苦しんでいるのでした。
黒澤明の呪詛
『夢』は好きな映画ですが、この「鬼哭」は凡作と断ぜざるを得ません。巨大化したタンポポや、角の痛みに苦悶する鬼など、視覚的に終末感を表現できる要素がありながら、環境破壊への憤りを7分半もの長台詞で延々と語るだけでは映画的な面白さに欠けます。核と放射能に対する憤りを描く点は「赤富士」と同じですが、たとえ訴える内容が正しくても、テーマをそのまま語らせることが説得力を欠いてしまうという失敗例になってしまいました。
水車のある村
あらすじ
美しい自然に囲まれた村を「私」は訪れます。水車小屋の前で水車の手入れをしてる103歳の老人は、この村が電気も無い昔ながらの生活をしていることや、科学の悪用が人間を不幸にすることなどを語ります。やがて、お祭りのように陽気な葬列がやって来ます。よく生きて、よく働いて天寿を全うした人を称えて送り出すというのが本来の葬式だと言い残し、老人もその葬列に参加するのでした。
黒澤明の桃源郷
ところで、スティーヴン・プリンスはコメンタリーで、このエピソードは電気の無い生活を讃えているが、電気が無ければ黒澤は映画そのものを撮ることが出来ないし、これほどの世界的名声を得ることもなかっただろうと批判的に語っています。一理あります。Blu-rayの特典映像のインタビューで、野上照代も、スマホ等の文明の利器と無縁の生活には中々戻れないと語っていましたし。
ただ、見方を変えると、このエピソードは、近代文明の否定よりも過去の素朴な生活に対する郷愁の方が色濃く出ているような気がします。
事実、黒澤が中学時代に訪れた父の故郷である秋田県仙北群豊川村(現・大仙市豊川)での体験が反映されています。死者を弔うため大きな石に子供達が野の花を摘んで載せる風習や、生きているというのは面白いという老人の言葉が、映画で再現されています。
それに、文明の利器に依存して生きているのだから近代科学を否定するべきではない、というのも傲慢な気がします。
確かに、科学の発達は私達の生活を豊かにしてくれて、現代人の生活は電気など近代文明なしでは成り立ちません。ですが、便利さの反面、大量破壊兵器や公害など近代化の悪用が人間や地球に深刻な被害をもたらしたことも事実です。サタジット・レイも遺作『見知らぬ人』(1991) で訴えていたように、核兵器で世界を破滅に導く人間は本当に文明人と言えるのか今一度考えてみる必要もあるのではないでしょうか。
そのように考えてはみたものの、やはり8分半もの間、メッセージを生のまま喋るというのは、やはり不自然な感じが否めません。「私」役の寺尾聰も、老人役の笠智衆も好演でしたが、最後のエピソードでも台詞に頼りすぎる欠点が露呈してしまいました。
それでも、「水車のある村」は、『夢』の締め括りとして最高の見せ場を提供してくれます。99歳で大往生した老婆を村民が総出で弔う葬列は、まるでお祭りのように賑やかで楽しく行進していきます。
葬列の楽隊が奏でる音楽について「どこの国とも、どこの時代ともわからない民族音楽」という黒澤の注文を受けた池辺晋一郎は、トルコの軍楽隊を思わせる高揚感溢れる素敵な曲を作曲しました。
主人公が村を去った後、アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972) を思わせる川の流れで映画は幕を閉じます。エンド・クレジットに流れるのは、イッポリト・イワーノフ作曲の《コーカサスの風景》より「村にて」です。リムスキー・コルサコフに師事したイワーノフは、コーカサス地方のグルジア国で民族音楽を研究して《コーカサスの風景》を作曲したそうです。そのため、ヨーロッパのクラシック音楽とは一味違う土俗的な響きが印象的です。
『夢』を締めくくる「水車のある村」で描かれたのは、東洋や西洋といった垣根を超えた素朴で幸福な世界です。それは黒澤明の過去の思い出に対するノスタルジアであると同時に、巨匠が未来の世代に伝えておきたかった平和への希求でもある筈です。
まとめ
『夢』は、黒澤明が個人的に撮りたい夢を撮った「プライベートシネマ」とも言える映画です。それ以前も黒澤は自分の撮りたい映画を撮ってきましたが、観客を楽しませるための工夫も凝らしてきました。黒澤が自らライフワークと呼んだ『乱』以降の3作では、一人で脚本を書くことで、より個人的・遺言的な内容へと変化していきました。
そうした性質上、過去の作品以上に批評家の賛否や観客の好みが大きく分かれるようになっていきました。勿論、私も『夢』の全てが良いと言う訳ではありませんし、先述のように欠点も少なからずあります。
ですが、そうした欠点を差し引いても、『夢』は補って余りあるほどの魅力に満ちていています。
公開から早くも30年が経ち、映像技術も進歩しましたが、『夢』で黒澤明が描いた数々の映像美は今も色褪せず鮮烈です。
(敬称略)
.
参考資料(随時更新)
書籍
『黒澤明 集成』 キネマ旬報社、1989年
『夢』 黒澤明、岩波書店、1990年
『夢』 松竹株式会社事業部、1990年
『何が映画か 「七人の侍」と「まあだだよ」をめぐって』 黒澤明、宮崎駿、徳間書店、1993年
『黒澤明 音と映像』 西村雄一郎、立風書房、1998年
『村木与四郎の映画美術 [聞き書き]黒澤映画のデザイン』 丹野達弥 編、フィルムアート社、1998年
『黒澤明 夢のあしあと』 黒澤明研究会 編、共同通信社、1999年
『蝦蟇の油 自伝のようなもの』 黒澤明、岩波書店、2001年
『黒澤明を語る人々』 黒澤明研究会 編、朝日ソノラマ、2004年
『KUROSAWA 映画美術 編 ~黒澤明と黒澤組、その映画的記憶、映画創造の記録~』 塩見幸登、河出書房新社、2005年
『黒澤明VS.ハリウッド 『トラ・トラ・トラ!』その謎のすべて』 田草川弘、文藝春秋、2006年
『大系 黒澤明 第3巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2010年
『大系 黒澤明 第4巻』 黒澤明 著、浜野保樹 編、講談社、2010年
『もう一度 天気待ち 監督・黒澤明とともに』 野上照代、草思社、2014年
音楽・映像ソフト
CD『「夢」「八月の狂詩曲」「まあだだよ」』 池辺晋一郎、東宝ミュージック、AK-0014、2002年
DVD『黒澤明 創造の軌跡 黒澤明 “THE MASTERWORKS” 補完映像集』 東宝株式会社 映像事業部、2003年
Blu-ray Akira Kurosawa’s Dreams. The Criterion Collection, 2016.
原発・核兵器関連
「原発問題 全般」
「原発は安くない」
「原発と石油」
「原発は温暖化対策にはならない(原発も二酸化炭素を排出する)」
「東京電力福島第一原子力発電所は(津波の前に)地震で壊れていた (そして、津波は予測されていた)」
「東京電力福島第一原子力発電所事故の放射能汚染による被曝症状」
「除染の問題点」
「御用学者」
「原発とメディア」
「核(人体)実験」
「海外の脱原発」
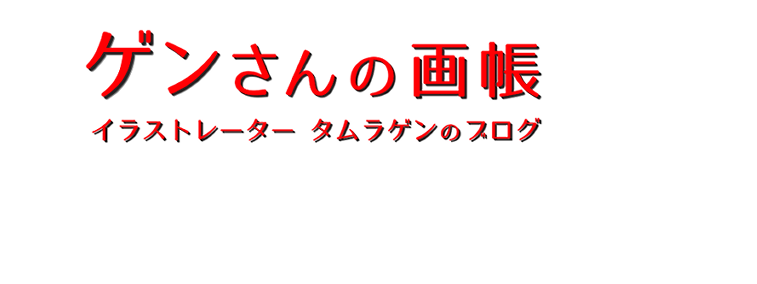






コメント